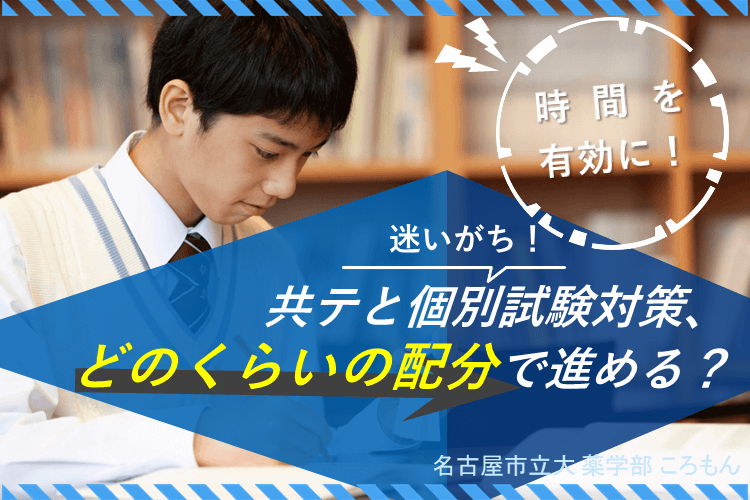
みなさんこんにちは!
2学期も中盤にさしかかってきましたが、みなさん受験勉強は順調ですか?
今日のテーマはズバリ、「共通テストと個別試験対策はどんなバランスで進めるべきか?」です!
本番が近づくにつれて、共通テストと個別試験対策の勉強バランスに悩んでいる方もいると思います。
私が、高校3年生の時のことを思い出しながら話していきたいと思います!
志望大の得点配分に合わせる
勉強バランスを考えるにあたって1番大切なのは、【志望大の得点配分を確認する】ということだと思います。
例えば、私の志望大は共通テストが9科目で500点、二次試験が3科目で600点でした。
このことから分かるのは「二次試験の1科目あたりの配点が高い」ということです。
そのため、二次試験対策で使用する科目に関しては二次試験対策を中心に、共通テストのみの科目はバランス良く取り組むことを意識していました。
また、共通テストの科目に関しては、科目によって得点の圧縮率が異なっていたため、【得点配分の大きさ】を意識して勉強をしていました!
今一度、本番での目標点数を確認することも、勉強バランスを考えることに役立つと思うのでぜひ考えてみてください!
メリハリをつけて学習をする
やるべきことが沢山あるなかで"残りの時間で何を優先したらいいのか..."とふと思う瞬間はありませんか?
私は、何か1つの科目に取り組み始めると予定していたよりも長く勉強してしまい、他の科目の勉強時間に影響を与えてしまうということがありました。
共通テスト対策、個別試験対策の勉強においても同じようなことを起こさないために【学校では共通テスト対策、家では個別試験対策の勉強をする】と決めていました。
私の学校では12月から授業が共通テスト対策になっていたので、学校では共通テスト対策を進めたい気持ちになっていたこと、また、個別試験の問題は1問あたりにかける時間が長くなるためまとまった時間を確保できる時に取り組みたいと思っていたことが理由です。
このように、何の対策をするのか自分の中で決めていた事によって、気持ちをその場その場で切り替えて勉強を進めることができたと思います。
どこで何の勉強をするべきか迷っている方は、よかったら参考にしてみてください!
最後に...
今回のポイントは、
①志望大の得点配分に合わせた勉強を心がける
②メリハリをつけて学習をする
の2点です!
本番が近づくにつれて緊張したり焦る気持ちになることもあると思います。
しかし、そのような時には【目標を再確認】してやるべきことにしっかりと取り組んでいって欲しいと思います!
何か困ったことがあればいつでも先輩ダイレクトで相談してくださいね。
体調に気をつけて頑張っていきましょう!
応援しています!!
<この記事を書いた人>
名古屋市立大 ころもん
※この記事は、公開日時点の情報に基づいて制作しております。


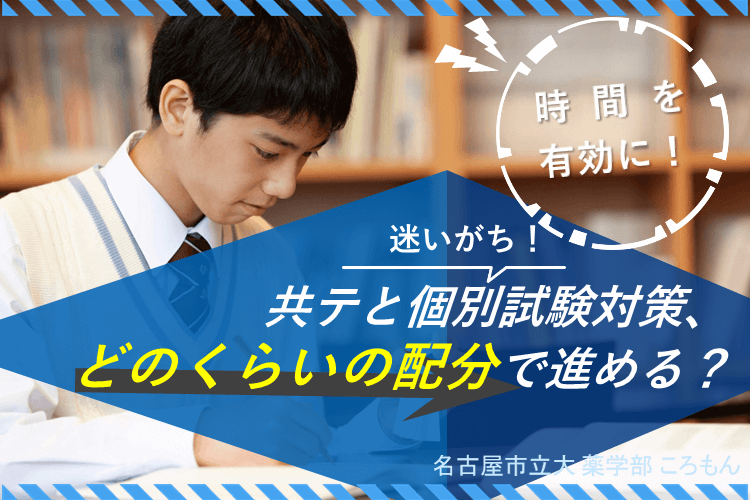





記事にコメントする
【コメント送信前に必ずお読みください】
このコメント欄では、質問や相談はできません。