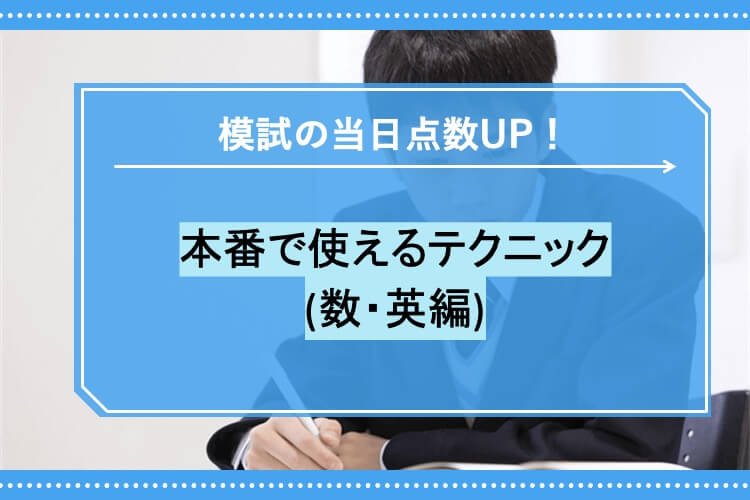
みなさん、こんにちは!
香川大学医学部のふゆはるです!
今回のテーマは、「模試の当日点数UP!本番で使えるテクニック(数・英編)」です!
ぼちぼち模試の点数や判定が気になり出してくる時期かなと思います。
そこで、模試本番で使えるテクニックを紹介したいと思います。
この時期の高校2年の模試の多くは、英国数の3科目が一般的だと思いますので、僕自身が特にテクニックを意識していた数学と英語のテクニックをご紹介します!
数学「3周得点法」+「ゴリ押し部分点稼ぎ法」
まず、数学の当日得点UP術です。
みなさん、数学の模試の得点が伸び悩む原因は何だと思いますか?
多くの場合は時間が足りない場合と、アイデアが思い浮かばない時、の2種類だと思います。
特に共通テスト形式のマーク模試だと時間が足りないケースが多く、記述模試だとアイデアが浮かばないケースの方が多いと思います。
マーク、記述ともに時短術は活用できるので、まずはそちらに目を通していただいて、アイデアが出ない時の考え方も、特に記述問題では有効になるケースが多いと思うのでぜひ活用してみてください。
「3周得点法」(時短テクニック)
① 全ての問題に目を通す(1周目)
② わかる問題から解く(2周目)
③ 時間がかかる問題は後回し(3周目)
まずは、時短テクニックの紹介です。
数学の問題で時間が足りないケースは計算時間が長い、or悩む時間が長い、というのが一般的だと思います。
計算時間が長いのは、試験時間中ではどうにもならないので日頃の学習でレベルアップしよう、という話になってしまいますが、悩む時間が長い、というのは試験時間の使い方でも解決しやすいのでここにフォーカスしていきます。
①全ての問題に目を通す
まず①で大切なのは、いきなり問題を解き始めず、最初の30秒〜1分以内で各大問にザーッと目を通して、相性の良さそうな問題、悪そうな問題を把握してほしいということです。
ここが1周目ですね。
よく、いきなり頭から解き始める生徒さんを目にしますが、そのようなタイプに限って後半の大問を丸々全部落としてしまっているというケースを目にします。
しかも、その大問の難易度は意外と高くなく、もっと点数が取れたのに、というのもよくよく見られるので、これをまずは避けたいというところです。
まずは、問題に目を通して自分にとって相性の良い大問はどこか、すぐに答えを導けそうな問題はどこか、など把握する時間を作りましょう。
②わかる問題から解く
最初の①の項目で相性などを把握したら、すぐに終わりそうな問題から順番に片付けていくということが大切です。
ここが2周目になります。
例えば、各大問の(1)の問題は、公式に代入すれば解けるような問題が出題されるケースが多いです。
そのような問題を確実に解き切るために、すぐに終わりそうなところだけをやっつけていきます。
個人的な感覚ですが、30秒以上解法が思いつかない、アイデアは思いつくけど計算式にして解くのには最低でも1分以上はかかる、みたいな問題だと、後回しにするかなというところです。
そのような感覚で、悩まず計算すればすぐに答えが出る問題をどんどん解いていきます。
すぐに解ける問題の解き残りを全ての大問で0にするようにします。
③アイデアや解法に時間がかかる問題は後回し
先ほどの問題で計算問題を解けばすぐ答えが出る、みたいな問題はなくなっていると思うので、ここから3周目です。
おそらく3周目については、結構ヘビーな問題が残っていると思うので、ここからは結構時間がかかる問題が多いでしょう。
そこで、残った問題の中でも、どこかの問題集で見たことのある問題、立式は簡単で計算だけがしんどい問題、アイデアに悩む時間は比較的少ない問題、というものを先回しにして、アイデアで時間がかかる問題を後回しにするというのが大切です。
例えばその大問に(1)〜(4)まであるような問題で、(3)まで終わったけど(4)は見たこともなく、かなり難しくて全くアイデアが思い浮かばない、みたいなケースが想像できますが、この場合は(4)は一旦捨てて、別の大問にいく、ということをここのステップでお勧めしたいと思います。
その他の問題を丁寧に時進めていくことができれば、おそらく3周目が終わった頃にはタイムアップになっていると思います。
このような3周得点法、と僕が勝手に呼んでいるこの解法をぜひみなさんに体得してもらえると、時間が足りていれば絶対解けていた、という問題はほとんどないと思います。
(時間が足りていればもしかしたら解けたかも、という問題は残ってしまうと思いますが・・・)
「ゴリ押し部分点稼ぎ法」(アイデアでない時)
① 絵やグラフ、表を描く
② 実験する
③ 問題を簡単な次元に落として考える
次にアイデアが出ない時の対策法です。
多くの高校生に多いのは、アイデアが思い浮かばないので全くペンが動きませんでした、というケース。
数学ができる人は、解法が思い浮かばないときは自分の手を動かして閃くまで挑戦するということが共通点としてあると思っています。
その中で、闇雲に手を動かしても意味が少ないので、その方針を紹介したいと思います。
①絵やグラフ、表を描く
これは、関数系、確率、数列、図形系(ベクトルを含む)タイプで使える考え方といえます。
例えば、関数で式が与えられていたら、とりあえずグラフを書いてみる、図形に関する情報が与えられていたらとりあえずそれっぽい図形を書いてみる、みたいなことをしていくと、その中で規則性や法則、数字のイメージ見たなものができるケースがよくあります。
そこから得たイメージをもとに勘で式を作るのは決して良いことではないのですが、それで正解が出るケースも結構あるので、まずは絵やグラフ、表などを書いてみてほしいです。
また、試験や採点官にもよりますが、このような途中の足跡みたいなものに部分点をくれるケースもあります。
②実験する
上記①と被るところもありますが、実験をしてみるというので、特に確率や数列において自然数が絡むようなケースであれば、n=1から順番に代入してみればいいじゃないか、みたいな発想が僕の中ではあります。
n=1や2ではあまり意味が少ないですが、5〜6くらいまで代入していくと、何となく式はこれじゃないか、みたいな勘が浮かぶことがあります。
記述問題の時、これで正解を出すと満点はもらえなくても部分点を取りに行けるチャンスが増えるので、粘るという意味では結構大切じゃないかと思います。
③問題を簡単な次元に落として考える
ここは結構数学らしい考え方と思いますが、わからない問題を解くためのパーツに分解するということを考えてほしいと思います。
例えば、四角形の面積を求めたいときに、四角形の長さが一部わからない、となると、その長さを出したい→そのために、角度などを求めて三角比を用いたい→三角比を用いるためにこの公式を使いたい、みたいに考えるべき項目を細分化していくと手をつけやすくなるケースも多いです。
いきなり問題や回答を導くのは難しいものがあると思いますが、細分化して求めるべきものを小さくしていくと、そこに伴って考えやすくなります。
また、記述問題の部分点は、答えの手前の段階までで各項目で何点、みたいな形で部分点を設定しているケースも多いので、答えに辿り着けなくても部分点稼ぎに役立つ可能性はあります。
綺麗に解くのも大事ですが、そうでなくても泥臭く解いていく姿勢を大切にしてほしいなと思います。
英語「時間戦略を見抜く」
① 全ての問題に目を通す
② すぐに解決する問題(悩まない問題)を終わらす
③ 配点の高い+時間をかけるべき問題を終わらす
英語の得点が出にくいのは、ひとえに時間配分の問題だと思います。
もちろん技術的にまだまだ英語を読めていないケースは多くあると思いますが、そうでなくてもなかなか時間が足りなくて、解き切れていればもっと得点が出たのに、みたいなことはよくあります。
この時間戦略の部分でアドバイスさせていただきたいと思います。
①全ての問題に目を通す
これは数学と同じですが、問題を解く前に30秒〜1分で問題の形式や内容をザーッと把握するようにしましょう。
このときすぐに解けそうか否かという目線で問題に目を通してみてください。
その際に、自分が問題集で見たことあるなとか、このテーマの文章は得意だな、苦手だな、みたいな目線でサッと目を通せれば、その後の項目につながっていきやすくなります。
②すぐに解決する問題を終わらす
例えば、文法や発音問題、会話問題などは比較的知識問題だと思いますから、ここは悩まずサッと解き進めて行ってほしいですね。
もちろん考えて根拠を持って回答するのは大事ですが、2択で迷う時間があれば長文の問題でもっと配点の高い問題に時間をかけられると思うので、なるべく悩まず解くように心がけましょう。
個人的には時間が足りないタイプの高校生については、知識系問題は1問MAX 1分(できればそれ以下)のイメージで解くのが時間管理しやすいと思います。
③配点の高さ+相性の分析→時間をかけるべき問題を見抜く
これは英作文や長文問題を念頭に置いています。
どの問題が自分に相性が良いかを把握し、かつ配点の高さを加味して、時間をかけるべき問題の順序を把握し、その順序通りに解いていくということを意識してほしいと思います。
相性の悪い問題で考える時間を長くしてしまうよりは、相性の良い問題で少しでも短い時間で得点を稼ぎ、また、相性の悪い問題も部分点だけもらっていくということで、同じ時間でも比較的多く点数を稼ぐことができます。
共通テスト型の時は、事前に解く大問の順番を決めていくケースもあると思うのでその限りではないですが、記述模試の時は瞬時に相性を見極められるか、でかなり得点効率がUPすると思うのでぜひ意識してもらいたいです。
まとめ
今回は以上になります。
ここまでの内容は試験のテクニックの一部にすぎません。
また、人によってはこの通りにしてもうまくいかない、もっと良いほうがある、というケースはあります。
そのため、不安な人、困っている人は、ぜひ先輩ダイレクトで質問してくださいね!
今回の内容や先輩ダイレクトを生かして、次回の模試からさらに点数を上げていきましょう!
頑張ってください!
応援しています!
<この記事を書いた人>
香川大 ふゆはる
最近は毎週レポート、試合、とドタバタで忙しいいですね(泣)
みなさんに負けないように頑張りたいと思います!
※この記事は、公開日時点の情報に基づいて制作しております。


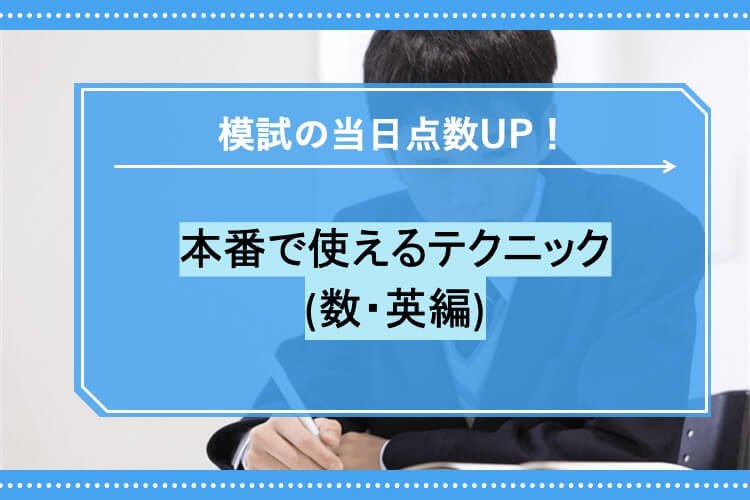





記事にコメントする
【コメント送信前に必ずお読みください】
このコメント欄では、質問や相談はできません。