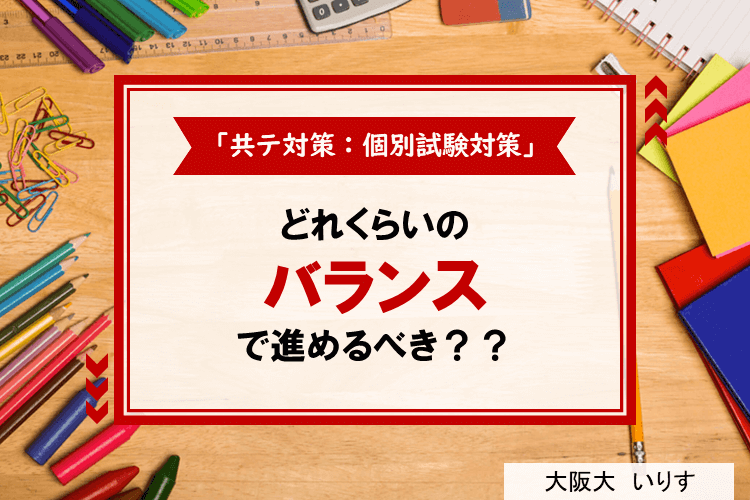
みなさん、こんにちは!
大阪大学人間科学部のいりすです。
10月も下旬になりましたね。入試本番ががいよいよ近づいて来たように感じているかもしれませんね。
勉強の計画はしっかり立てられていますか?共通テストと個別試験の勉強のどちらを優先するべきか迷っている人も多いのではないでしょうか?
今回は、私の経験を元に「共通テスト対策vs個別試験対策の勉強バランス」について書いていこうと思います!
「点数の比率」&「得意・苦手」を見極める!
共通テストと個別試験の話に限らず、勉強の比率を考える上で最も大切なことは、「必要なもの」かつ「苦手なもの」を優先するということです。
だからこそ、まずは受験する大学・学部の「共通テストと個別試験の点数比率」を確認しましょう。
その次には、「どちらがより苦手か、点数が取れないか」を考えます。模試の点数などを参考にするのがオススメですよ!
私の場合、「共テ:個別試験の点数比率=50%:50%」だったので、「どちらも同じくらい重要」と判断していました。二ガデ度合いに関しては、「個別試験はかなり得意、共テが完全に足を引っ張っている」状況でした。
この2つを合わせて考えた結果、12月頃までは「共テ:個別 = 9:1」くらいのバランスで勉強していました!
「基礎力の底上げ」を図ろう!
ここまで勉強のバランスについて書いてきましたが、入試に向けた勉強で最も大切なことは、「どんな問題にも対応できるだけの基礎力」を付けることです。
基礎力が不十分だと、共通テストも個別試験もどちらも解き切ることが出来ません。
だからこそ、特に10月〜11月の勉強は、形式に囚われすぎない多様な種類の演習にも取り組んでみてください!
過去問などそれぞれの形式の演習にも取り組みつつ、失点した分野はワークなどに立ち返って復習・演習してみるのがオススメですよ。
「自分の弱点」補強で最強を目指そう!
勉強のバランスは、「自分の弱点」を見極めながら立てていきましょう。
共通テストvs個別試験の配分も、過去問演習と基礎力向上の配分も、
・必要度が高くて苦手なものは?
・どこを補強したら合格に近づく?
という視点で考えるのがポイントです。
そして迷ったら、まずは基礎力の底上げに戻ってみましょう。
英単語・古文単語・計算などの基礎は、どんな形式の試験にも効きます。
「バランス=基礎の延長線上」と考えれば、安心して勉強を進められますよ!
自分だけではぴったりな配分が分からない......個別に相談したい......そんな時はぜひ、先輩ダイレクトで質問してみてくださいね!
<この記事を書いた人>
大阪大 いりす
※この記事は、公開日時点の情報に基づいて制作しております。


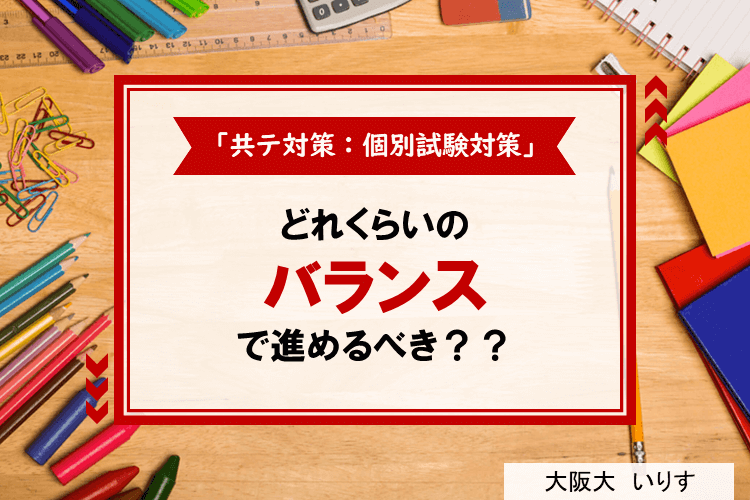





記事にコメントする
【コメント送信前に必ずお読みください】
このコメント欄では、質問や相談はできません。