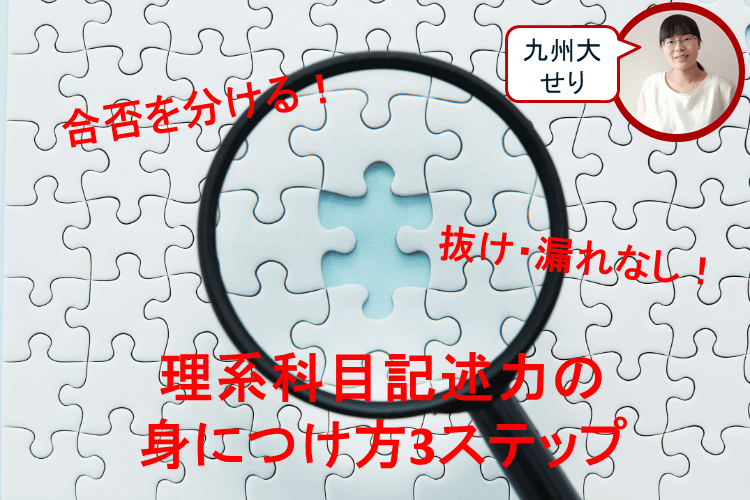
高3生の皆さん、こんにちは!
九州大学理学部のせりです!
そろそろ10月が近づいてきて、共通テスト対策も二次試験対策もどっちもやらないと...と焦ってしまう時期になってきましたね...
二次試験の大変なポイントはなんといっても記述試験が多いことです!
自分ではどこまで点が取れているかがよく分からず、模試などではなぜかちょっと点が引かれていたりして、満点がとりにくいのがネックですよね...
そこで今回は、理系科目の記述で減点されにくくなる書き方を3ステップに分けてお伝えしていきます!
考え方や公式・定理を使う流れを書いてみよう!
頭の中では分かっていても実際に人に伝わるように、抜けがないように記述していくのは難しいものです。
まず、なにをどの文字で置いたのか、どこ・どの性質に注目して考えて、式を立てたのか、なんという定理を使ったのかを、答えはこの値で妥当なのかを順を追って書いていきましょう!
世界で一番分かりやすい解説を作る気持ちで、事細かに書く練習をしていくことがおすすめです!
復習でノートを見返したときに、「昔の自分、不親切な省略解説くらいしか書いてないじゃん...」となっては復習しにくいので、後の自分のためにも丁寧に段階を踏んで記述していくことが大切ですよ!
解説を読んでブラッシュアップ!
自分で解答を作り終わったら、解説を見て、どこが絶対に書かないといけない部分なのか、定理や公式の使い方・名前が合っているかの確認をしていきましょう!
この時に、自分の解法と解説の解法・別解のどれが短く・速く解けそうかを見ておくことも大切です!
二次試験は時間が長いように見えて、考えているうちにすぐ時間が足りなくなります。
少しでもスムーズに解答ができるように、問題に合わせて自分が得意な解法とその記述の流れを確立しておくことが、総合得点アップにつながりますよ!
合格への100題の課題を提出しよう!
自分の解答が記述できるようになったら、合格への100題の添削課題を使って、実際に二次試験レベルの問題で自分の記述力を試してみましょう!
添削課題は最後までできなくても、解けたところまでの提出でも、記述で足りない箇所やつまずいた部分を解くのに必要な考え方・知識を教えてくれます!
記述力を身につけるためには自分以外の人に採点してもらうことが一番重要なので、難しくてなかなか手が出せなくても、自分なりに考えた筋道を書いて、提出してみることがおすすめです!
私は、ついつい「難しいから」という理由で合格への100題に取り組むのを後回しにしていたのですが、添削課題を出して返ってくる頃には、もう記述方法なんてブラッシュアップしているような余裕がなく、ひたすら解法を頭に叩き込むので精一杯な状況でした。
記述で点を落とさないためにも余裕をもって今のうちから対策しておくことが本当に大切です!
以上をまとめると、
1,まずは、自分の解き方・使う定理を順を追って言語化する
2,解説を読んで、考え方・必要な記述箇所が合っているかを確認
3,合格への100題で添削
という3ステップで減点されにくい記述力が身につきますよ!
この記事が少しでもお役に立っていたら嬉しいです!
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
<この記事を書いた人>
九州大 せり
※この記事は、公開日時点の情報に基づいて制作しております。








記事にコメントする
【コメント送信前に必ずお読みください】
このコメント欄では、質問や相談はできません。