皆さん、こんにちは!
大阪大学工学研究科のトラタローです。
ようやく酷暑が終わりつつありますね。
秋が近づいてきて、そろそろ過去問に手を付けようという人もいるのではないでしょうか。
そこで、今回は過去問対策の進め方について「共通テスト」と「二次試験」の二つの面からお話ししようと思います。
共通テスト対策
まずは共通テスト対策について。
共通テストは、時間との戦いが最大のポイントです。
実際に解いてみると、想像以上に1問あたりの持ち時間は短いため、限られた時間の中ですらすらと解き進める力が求められます。
私はこの時間に苦労させられたことをよく覚えています。
過去問や模擬問題を解く際は、時間を計測し、常に「あと何分で次の大問に移るべきか」を意識することが大切です。
初めは解ききれないことも多いとは思いますが、時間を意識した演習を繰り返すことで、問題を読むスピードや解答の手順が自然と最適化され、本番でも焦らずに解き切ることができると思います。
"知識"と同じくらい"時間感覚"を鍛えることが、共通テスト攻略の鍵です。
二次試験対策
二次試験は、難易度が高いことが最大の特徴です。
知識量だけでなく、深い思考力・論理構成力・答案表現力が求められます。
私は実際に20年分ほどの過去問に取り組み、その中で効果的だったと思う進め方があります。
今回はその方法を紹介させていただきますね。
まずは、時間を気にせずにじっくり解くことから始めます。
この段階では、教科書や参考書には頼らず、自分の頭の中にある知識と考え方だけで最後まで解き切ることを目標にします。
途中で詰まっても、別のアプローチを試したり、条件を整理し直したりしながら、自力で答えにたどり着く経験を積みます。
分からなかった問題は解答をすぐに見るのではなく、1週間ほど寝かせてから再挑戦します。
これは、一度頭を整理し、初回とは異なる視点や発想で再び向き合うためです。
これを繰り返すことで、思考力が付き難問にも対応できるようになったと思います。
仕上げの段階では、直近3年分くらいの過去問を本番と同じ時間設定で解くことが重要です。
ここでは「時間内に解ききる」ことを目標にし、答案の書き方や時間配分を本番仕様に最適化しました。
このように、"自分で解ききる力"を鍛えることが二次試験対策の鍵です。
今回の記事は以上です。
また何かわからないことがあれば先輩ダイレクトで質問して下さいね。
応援しています!
<この記事を書いた人>
大阪大 トラタロー
※この記事は、記事公開日時点の情報をもとにしております。


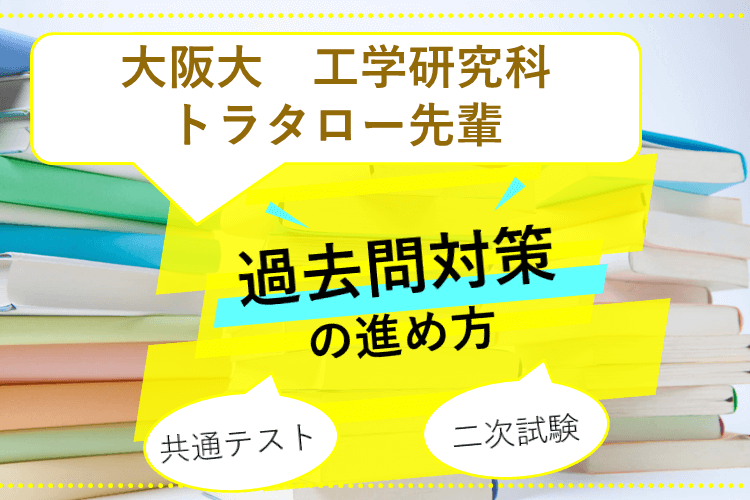





記事にコメントする
【コメント送信前に必ずお読みください】
このコメント欄では、質問や相談はできません。