こんにちは!
東京外国語大学 言語文化学部のパチアです。
あっという間に夏休みが過ぎ去り、もう9月になってしまった...というところでしょうか?
今年の夏はとにかく暑い!暑すぎる!!
ということで、暑さのダメージがまだ体に蓄積されているかもしれないので、引き続き体調管理には気をつけていきましょう!
さて、いよいよ演習が本格化してくる時期です。
![]() ちょっと危険な受験生
ちょっと危険な受験生
とにかく数をこなすために、闇雲に演習しまくるぞ!!
そんなあなたはちょっと待ったー!
演習を重ねることはもちろん大切なのですが、闇雲にやるのはもったいない!!
私は11月頃まで推薦入試の対策もしていたため、一般入試のみの人たちよりも、演習量は少ないと思います。
それでも、今回紹介する方法をやっていたことで、共通テストでは高得点を取ることができました!
今回は、私が実際に行っていた「実践につながる演習方法」を3つ紹介します!
共通テストはもちろん、二次試験にも役立つ方法になります!
①【解きながら】本番に向けて大問ごとの時間管理!
本番に向けて、大問ごとに時間を意識して解くのがオススメです!
適した時間配分というのは人によって違うもの。
だからこそ、早めのうちから、下記の2つを意識して演習をすることが大切です!
・どの順番で解くのか
・どの設問に何分かけるのか
早めのうちから試行錯誤をして、自分に合った方法を見つけたら、あとはその順番と時間配分に慣れるだけです!
①時間配分を考える具体的な方法
私の場合、具体的には、演習をしているときに、2つの時計を使っていました。
1.その科目全体の時間を測る用(アナログ時計)
2.各大問ごとの時間を測る用(ストップウォッチ機能を使用)
1つ目でアナログ時計を用いたのは、その方がパッと見で時間の経過がわかりやすいからです!
本番も使う予定のアナログ時計を、演習のときからずっと使っていました。
また、2つ目の時計で各大問ごとの時間を測ったら、問題用紙の各大問の近くにメモをしておきました。
それから、下記の分析をしました。
・どの順番で解くのが解きやすいと感じるか、また得点を多く取れそうか
・どの設問に時間をかけるべきで、どの設問の時間を短縮すべきか
①演習のうちから時間管理をするメリット
こうすることで、良かったことはこの2つです!
・時間内に、自分にとって最も効率よく得点するための解き方がわかってくる!
・緊張でたとえ頭が真っ白になってしまっても、いつもの慣れた順番とタイムスケジュールで解けばいい!
本番、自分の実力を存分に発揮できる土台となる、各教科のタイムスケジュールを作ることができます!
②【解きながら&復習】自信のない問題に印をつける!
問題を解きながら、自信のない問題に印をつけるのがオススメです!
丸つけのときには、つい間違えた問題にだけ注目しがち...。
しかし、実際には、結果的には正解だったけれども、自信がなかった問題などもあるはずです!
そこで、問題を解きながら印をつけておくことで、後で復習のときに偶然正解してしまった問題も振り返りやすくなります!
②印をつける具体的な方法
私の場合、具体的には、下記の3つの印を使っていました。
・△...一応答えは出せたけれども、自信がない問題
・△△...一応答えは出せたけれども、ほとんど自信がない問題
・×...全くわからない問題
②解きながら印をつけるメリット
こうすることで、主に良い点はこの2つです!
1.見直しの際に優先して確認すべき問題がわかる!
2.答え合わせ、その後の復習のときに、偶然正解していただけの問題も、抜け漏れなく確認できる!
偶然正解していただけの問題を放置していると、再び似たような問題に出会ったとき、「あれ、見たことあるのに自信ない...」となりかねません。
だからこそ、間違えた問題だけでなく、自信がなかった問題も復習しやすくする印付けが有効です!
③【復習】解答と解説だけで満足しない!
問題を解いた後、解答と解説を確認しただけで満足するのはもったいないです!!
というのも、入試本番に、演習したものと全く同じ問題が出ることは少ないからです!
私は、演習をする理由は主にこの2つだと考えていました。
・似たような問題が出たときに解けるようにするため
・自分が理解不足の分野を見つけるため
そのため、早く次の演習をしたい気持ちはわかりますが...
そこはグッと堪えて、復習にも時間をかけましょう!
復習の具体的な方法
私の場合は、演習をしたあと、下記の4点を行っていました!
1.間違えた問題や自信がなかった問題の解答解説をよく確認する
2.1で確認したところを教科書(※)で確認する
※英単語や古典単語が原因のときは単語帳
※英文法や漢文の構文が原因のときは文法書
※教科書に載っていない場合は資料集や用語集
3.2で確認したところに、色ボールペンで線を引くなど、印をつけておく
4.周辺の関連するページも確認しておく
教科書に戻って復習したメリット
こうすることで良かったことが3つあります!
・間違えた部分や自信がなかった部分ピンポイントではなく、その周辺の知識もまとめて確認するようになるため、似たような分野が問われたときに正解しやすくなる
・印を残すため、教科書を復習のために読み直した際などに、自分のニガテな箇所がわかる
・同じような問題を間違えた際に、教科書を見ると印が残っているため、「似たような問題をまた間違えてしまった!」と気づける
ただ解答解説を見るだけでは演習の効果は半減です!
大切なのは、演習を通して、自分の知識の抜け漏れをなくしていくことです!
【まとめ】演習は数だけでなく、質も大切!
今回の「実践につながる演習方法」のポイントはこちらです!
①時計のダブル使いで、タイムスケジュールを作る!試す!
②問題に印をつけて、「偶然正解」も見逃さない!
③教科書を使った復習で、周辺の知識もカバー!
この3つを使いこなせば、1回の演習の効果が何倍にもなるはずです!
もちろん慣れて、スピードを上げるために、数をこなすことも大切ですが、ただたくさん解けば良いというわけではありません!
本番に向けた戦略立て、復習の観点も意識して、演習に取り組んでみてください!
受験勉強で困ったら...
演習のやり方に関することでも何でも、何か気になることがあったら、気軽に「先輩ダイレクト」で質問してみてくださいね。
私への指名質問も大歓迎です!
\先輩への指名質問も可能/
もう9月、まだ9月です。
これからが伸びるために大切な時期です!
応援しています!!
<この記事を書いた人>
東京外国語大 パチア
休憩時間どう過ごそうかな、何のお菓子を食べるのがいいかな、なども考えて、試しておくと、本番いつも通りの感覚で過ごせますよ!
※この記事は、公開日時点の情報に基づいて制作しております。


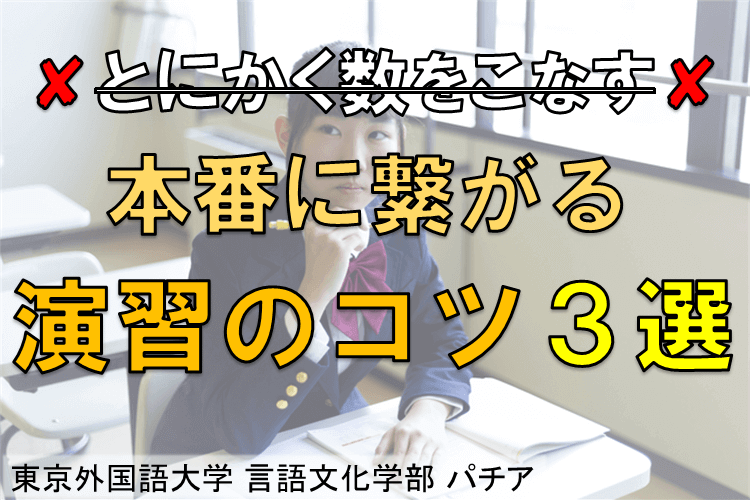






記事にコメントする
【コメント送信前に必ずお読みください】
このコメント欄では、質問や相談はできません。