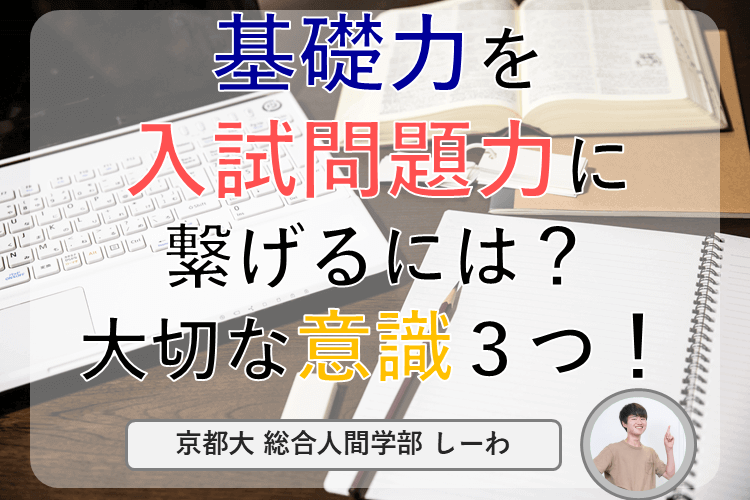
こんにちは!
京都大学総合人間学部の しーわ です。
夏休みが明け、入試勉強も基礎固めから徐々に本番を意識した過去問演習などに内容が変化していく時期かと思います。
そのような状況では今までは「とにかく基礎力」と考えてきたものを、徐々に入試問題を解く力へとステップアップさせていく必要があると思います。
このステップアップはとても難しくて、「なかなか過去問が解けるようにならない」みたいな壁にぶつかるのはあるあるだと思うのですが、僕の経験から「こう意識を変えると良いのではないか?」ということについて紹介したいと思います!
基礎の穴を減らす
1つ目は基礎固めの穴を減らすということです。
入試問題がなかなか解けない原因として、基礎固めの時に身についていなかった抜け穴の部分が積み重なって問題が解けなくなってしまうということが挙げられると思います。
覚えていない単語であったり、ど忘れした解法が引き金となって解けなかったということはよくあります。
そのために、基礎固めをしている段階から基礎の穴を減らすということがとても大事です。
今、基礎固めをしている人はなるべく抜け穴がないように徹底すること、もう一通り終わったという人は定期的に復習の機会をとって忘れないようにすること、がとても大事だと思います。
抜け穴があるかどうかのチェックは、最初から全部やり直すというより、不安があるところだけに注目すればOKです。
基礎固めの完成度を高めるということ、ぜひ意識してみてください!
「どうしたら解けたか」の見直しが大事
二つ目は、「どうしたら解けたか」と見直しをすることです。
入試問題のような難しい問題を解いたとき、ただ〇×をつけるだけでは実力は伸びません。
どう間違えたのかという見直しが当然重要です。それに加えて、どう間違えたのかを確認した後は、じゃあどうしたら解けたのかというところまで考えることが演習力を挙げるコツだと思います。
例えば、「この単語が分かっていれば解けた」「この文構造に着目するクセがあれば解けた」「問題文のこの部分からこの解法を思い出すようにすれば解けた」など、様々な分析ができると思います。
このような「どうしたら解けたか」ということまで一歩深く考えることで、自力で解けるようになる実践力が伸びていくと思います。
解き直しで「自力で解けた」経験を増やす
三つ目は、解き直しをして「自力で解けた」という経験を増やすことです。
見直しをただするだけではなく、間違えた問題を自力で解けるまで解き直すことはとてもオススメです。
理由としては、解説を読んで分かったつもりだけではなく「自力で解ける」という確証をとることがとても大事だと思うからです。
問題を「分かる」と「解ける」は別物で、この別物感は入試問題のような複雑なものになればなるほど強まると思います。
実際に手を動かして解けるようになり、自分が解ける問題の幅を広げることで、入試問題級の問題にも対応力が上がってくると思います。
見直しの後は解き直しまでをセットにして、ぜひ取り組んでみて欲しいなと思います。
まとめ
今回は、基礎力を入試問題力に繋げるための意識を3つ紹介しました。
どれも自分自身が受験生の時に意識していたことで、実践力に繋がったという実感があるものです。
過去問演習、記述模試、など基礎から一歩発展した力がちらつく時期だからこそ、その力に向けた勉強法を考えてみてください!
まだまだ暑いと思いますが、体調にだけは十分気をつけて頑張ってください!応援しています!
<この記事を書いた人>
京都大 しーわ
※この記事は、公開日時点の情報に基づいて制作しております。


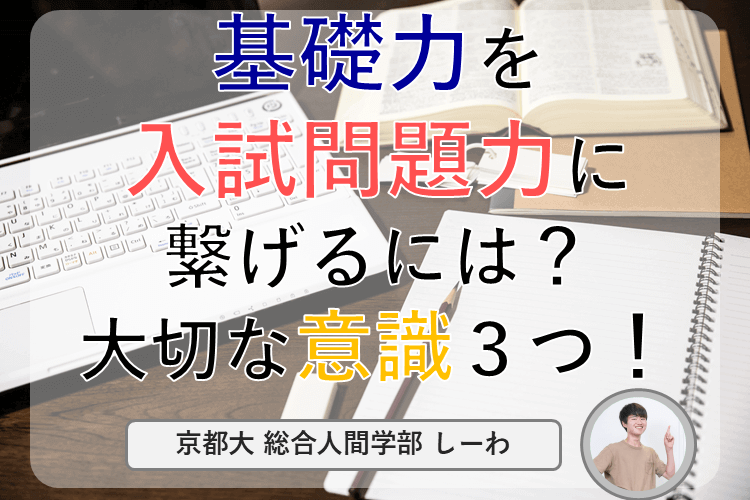





記事にコメントする
【コメント送信前に必ずお読みください】
このコメント欄では、質問や相談はできません。