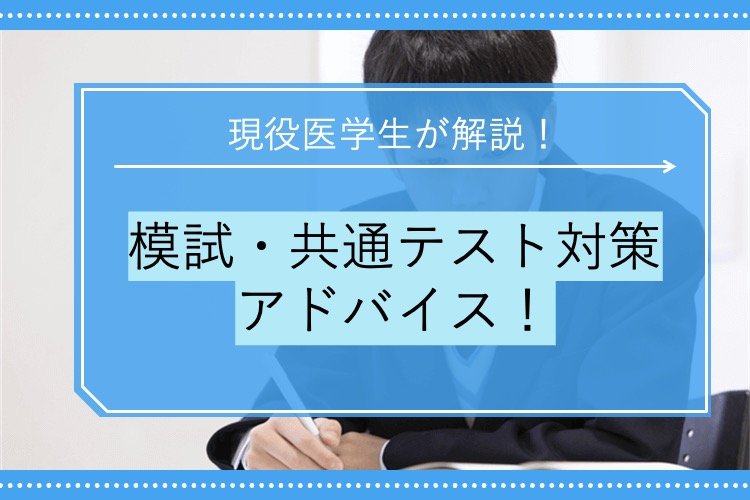
みなさん、こんにちは!
香川大学医学部のふゆはるです!
ぼちぼち夏休みも終わる頃ですが、勉強の進捗はいかがですか?
この夏休み限界突破の受験勉強をできた人は、自分のことをしっかりと褒めてあげてくださいね!
秋以降の模試ですぐに結果が出れば最高ですが、出なくても決して自分を卑下したり、自分を諦めたりせず前向きに進んでいきましょう!
さて、今回は模試と受験戦略についての今後の考え方をみなさんにご紹介したいと思います。
テーマとしては国公立医学部生向けの内容になるので、その他の大学の受験を検討している人には少し役に立たないかもしれませんが、参考になることもあると信じているので、少しでも興味があれば最後まで読んでくださいね!
模試の志望校欄の考え方
模試には、共通テスト型の模試と記述型の模試の2種類がありますが、そのどちらも紹介したいと思います。
共通テスト型について
まずは共通テスト型の模試については、国公立大の出願先の検討と私立大の共通テスト利用・併用型の入試について検討するのに活用しやすい、という特徴があります。
そこで今どこの大学を、判定を見れる志望校欄に記入するか悩んでいる人は、以下の考え方を参考にしてもらえればと思います。
①第1志望の国公立医学部
②第2志望の国公立医学部
③(志望校ではないかもしれないが)比較的入りやすい国公立医学部
④国公立で医学部以外で出願先にしても良いと思える大学
⑤共通テスト利用を検討している滑り止め校、または併願校
一般に模試の志望校欄は8校かけることが多いので後の3つは自由に書いていただければ良いと思いますが、5つについてはお勧めです。
僕自身、①、②は当時最優先で考えていた2校を記入しました。
そして、③に地元である香川大学を書いていました。
そして④に該当する大学として東北大学、⑤に該当する大学として東京理科大学、立命館大学を書くようにしていました。
④、⑤を書くことにプライドが邪魔をする人もいるかもしれませんが、受験は現実と向き合わないといけないので、共通テストがうまくいかなかった時用の大学を用意するのは戦略として大事です。
また、④、⑤の大学については過去の模試でほとんどの医学部でE判定とかであればおそらく旧帝レベルの大学はあまり良い判定ではないと思うので、例えば④の選択で言うと、西日本で言えば神戸大学、広島大学、東日本で言えば横浜国立や千葉大学、という選択肢を検討すると言うことで書く方が良いのかなと思います。
記述型について
記述の場合は、私立大学の個別試験や国公立の記述型の判定、さらには共通テストとのドッキング判定を考える必要があるので、共通テストとは別の大学を記入する必要があります。僕が思う書くべき大学を以下に示します。
①第1志望の国公立医学部
②第2志望の国公立医学部
③(志望校ではないかもしれないが)比較的入りやすい国公立医学部
④国公立で医学部以外で出願先にしても良いと思える大学
⑤私立大学の個別試験を検討している大学
①〜④は共通テストの時と同じですが、僕の場合は④について東北大学ではなく東京工業大学(現在は東京科学大学)を記入していました。
理由としては東京工業大学は共通テストの得点を合否判定に使わないシステムだったためです。
そして、⑤については、私立大学の医学部を検討していたため、自治医科大学、昭和大学(現在は昭和医科大学)、慶應義塾大学の理工学部などを書いていました。
このような形で模試の志望校欄は模試の形式によって変化させることが大切であると言うことを理解してもらえれば嬉しいです。
今どこの大学を書こうか、と悩んでいる人がいればぜひ参考にしてください。
共通テスト対策について
ぼちぼち共通テスト型の模試も増え、共通テストの時期も迫ってきて、学校の授業でも共通テスト対策をしましょう、みたいな話を何度も聞くことになると思います。しかし、共通テスト対策について間違って捉えている人が多くいるので、ここで紹介しておこうと思います。
大切なことは、共通テスト型の問題をたくさん解く≠得点UP!
共通テスト対策と聞くと、過去問演習や市販の共通テスト実戦問題集、みたいなものをたくさん解けば成績が上がる、と考えている人が多くいるのですが、それは明確に間違いです。
と言うか、解けば解くだけ点数が伸びれば多くの人が8割とか9割くらい取れてしまって試験の意味をなさない、と言う可能性が出てきます。
そのため、この考え方は行きすぎた考え方であると言うことを理解してもらう必要があります。
ただし、共通テスト演習が得点を上げる上で必要ないわけではありません。
問題の傾向になれること、問題ごとの時間配分を設定すること、自分の苦手な範囲がどこかを理解すること、などと重要な要素もあります。
そのため、共通テスト型の演習をする際には、自分が今何のために共通テスト演習を行なっているのかと言うことを意識して勉強しましょう!
オススメのスケジュールは以下の通りです。
9月:2週間に1回(形式を把握+対策を立てる)
10月:1〜2週間に1回(立てた対策が有効か判断するため)
11月:1週間に1回(対策が不十分+自分の苦手発見)
12月:3日〜7日に1回(苦手発見+スピード感など共通テスト慣れ)
1月:共通テストまでに1〜3回(戦略のチューニング+最後の詰め確認)
また、共通テストの点数を上げる最も大事なポイントは、日頃からの参考書などによる演習や学習なので、共通テスト演習をしない日は積極的に受験用の演習教材を実践していきましょう。
まとめ
今回は模試の志望校欄、共通テスト対策についてざっくりと触れてきました。
ただし、あくまでここに僕が書いていることは一般論に過ぎません。
人によって全く受験の戦略は異なってくることがあるので、今のままでいいのかなとか、もっと詳しく話聞いてみたいな、と言う場合は遠慮なく、先輩ダイレクトで質問をしてくださいね!
ここから激動の9月、10月と過ごしていくことになりますが、体調管理に気をつけて精一杯頑張ってくださいね!
応援しています!
<この記事を書いた人>
香川大 ふゆはる
僕が共通テスト対策に本格的に取り掛かり始めたのは11月からでした。
もう共通テストの勉強も、共通テストの受験もしたくないほど過酷だったことを覚えています。(泣)
※この記事は、公開日時点の情報に基づいて制作しております。


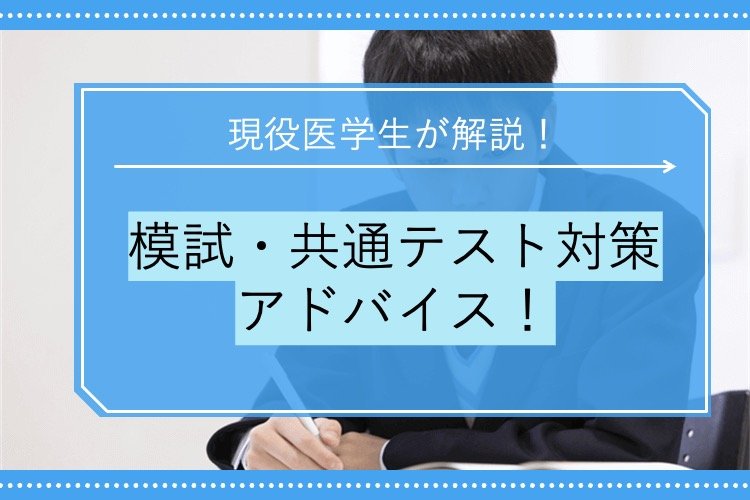





記事にコメントする
【コメント送信前に必ずお読みください】
このコメント欄では、質問や相談はできません。