皆さん、こんにちは!
近畿大のラリマーです!
皆さんは、志望大は決まりましたか?
まだ決まっていない人は、夏休みにオープンキャンパスに参加したり、大学紹介を見たりして考えてみてくださいね!
一方で、既に志望大を決めていて、「学びたい学部が見つかった!」「憧れのキャンパスライフが待っている!」という人も多いと思います!
実は私自身、「週6日・片道2時間」で大学に通っています。
そのため、決断する前に一つだけ、本気で考えてほしいことがあります。
それは、「その大学、本当に4年間通える?」という疑問です。
見落としがちな「通学時間」や「通学方法」。
実は、この2つは"あなたの大学生活の充実度"を大きく左右する、超重要な問題です!
そこで今回は、私の経験談を踏まえて、「通学」を重視した志望大の考え方を紹介します!
4年間の大学生活が「移動」で消える?通学時間の恐ろしさ
大学生活は4年間、単純計算で約1,460日です。
もし、ごく一般的な例として、あなたの通学時間が片道1時間半、週5日大学に通うとすると...
3時間×週5日×40週×4年間=2,400時間
この2,400時間という数字を、あなたはどう感じますか?
これは、丸々100日間に相当する時間です。
この膨大な時間を「有意義な学習時間」にできるか、「ただ疲れるだけの苦痛な時間」になるかによって、大学生活の質は大きく変わります!
通学時間の限界ライン
私の周りにも、片道2、3時間かけて通学する友達が多くいました。
私の友達の経験から見えてきた「通える/通えない」通学時間の限界ラインを紹介します!
◎セーフライン:【片道1時間半以内かつ電車で座れる】
このレベルであれば、実家からの通学を継続できる可能性が高いです。
「電車で座れる」というのが最大のポイント。
移動時間を、課題や予習をする「勉強時間」、本や動画を見る「休憩時間」、貴重な「睡眠時間」に変えられます!
体力的な負担も少なく、無理なく大学生活を送れると思います!
実際に、通学時間が1時間半以内で電車に座れる友達は、全員最後まで実家通いを続けていました。
△イエローゾーン:【片道1時間半超または立ちっぱなし1時間以内】
片道1時間半を超えたり、1時間程度でもほとんど立ちっぱなしだったりすると、通学が厳しくなってきます。
実際に、私の友達は以下のような工夫をしていました。
・履修を工夫し、大学に行く日を減らす
「1、4限に授業」のような"空きコマ"が多い時間割を避け、授業を特定の曜日に集中させる。
週3〜4日の通学で済むようにして、体力的な負担を軽減する。
・忙しい学年だけ下宿する
実験や実習、ゼミ活動で忙しくなる2・3年生の間だけ、大学の近くで一人暮らしをする。
このラインにいる人は、「どうすれば負担を減らせるか?」という戦略的な工夫が必要になります。
×レッドゾーン:【片道3時間程度または立ちっぱなし1時間超】
正直に言うと、このレベルは実家からの通学は極めて困難です。
「立ちっぱなし」では、勉強や作業がほぼ不可能で、体力を消耗するだけの時間になってしまいます。
多くの友達が「立ちっぱなしの限界は1時間まで」と言っていました。
・毎日3時間かけて大学に着く頃には疲れて授業に集中できない。
・授業や部活等で夜遅くなると、帰宅は深夜。
・次の日が1限からだと、睡眠時間はほとんど確保できない。
これでは、大学での勉強、課外活動、友人関係、全てが中途半端になってしまう恐れがあります。
大学までの通学経路を調べよう!
大学までの通学経路を調べる方法は、「机上調査」と「現地調査」の2種類があります。
実際に行くことで、より通学の大変さがわかると思います!
机上調査:アプリとHPを駆使して調べよう!
・乗り換え案内アプリ
自宅の最寄り駅から大学の最寄り駅まで、1限がある時の電車等の時間とルートを検索してみましょう!
・大学のHP
「アクセス」のページを必ず確認しましょう。
「〇〇駅から徒歩20分」と書かれていたら、それは毎日往復40分のウォーキングが確定します。
バスがあっても1限の時間帯は混み過ぎて乗れない、6限の時間は出ていないこともあるので、バスの本数や徒歩での所要時間も調べておきましょう。
現地調査:実際に行って確かめよう!
これが一番確実です。
オープンキャンパスや入試で大学へ行く際に、必ず「普段通うことになる時間帯」に家を出てみてください。
・電車の混雑具合は?座れる?
・乗り換えはスムーズ?
・駅からキャンパスまでの道は?(坂道が多いと想像以上に体力を消耗します)
・雨の日や暑い日の通学は耐えられそう?
調べただけの時と、実際に体験した時ではかなり感じ方が変わります。
「これなら大丈夫」「これは無理かも...」というリアルな感覚が得られるはずです!
「下宿」は最強の投資かもしれない
もし、あなたの志望大の通学時間が「イエローゾーン」や「レッドゾーン」に該当するなら、「下宿して大学の近くに住むこと」をきちんと考えてみてください。
「お金がかかるから...」と諦めるのはまだ早いです。
通学にかけていた膨大な時間を、大学の図書館での勉強、研究や実験、サークルや部活、アルバイトなどに充てられます!
特に、アルバイトで生活費や家賃の一部を稼ぐ選択をする先輩もいます。
大学が提供している寮や、奨学金制度を調べるのも1つの手段だと思います。
「時間」と「体力」、そして「充実した経験」を得るための自己投資として、「下宿」という選択肢を考えてみてはいかがでしょうか?
私のリアルな体験談:教職課程+部活動を両立した場合
「教職課程を取りたいけど、忙しいのかな?」、「部活やサークルも頑張りたい!」という人のために、私の体験談を載せておきます。
私は、学部で取れる4つの資格のために多めに授業を受けながら、社会の教員免許を取るための教職課程も追加で履修していました。
さらに、3年まで大学の天文部にも所属していたため、毎日忙しかったです。
私の1日のスケジュール(忙しい時期)
・6:00起床、6:30出発(電車内は課題を進めるか、仮眠をとるかの二択)
・9:00〜20:00(1限から6限までの授業+教職課程+部活動)
・20:00〜22:00(大学祭が近づくと、休憩時間も返上で準備作業)
・22:00大学を出発
・0:00帰宅(終電に近づくと電車の本数も減り、移動にさらに時間がかかることも...)
・帰宅~夜明け前まで 夕食と入浴後、課題やレポート作成(ここが一番の勝負でした...!)
教職課程は通常の学部の単位に加えて取る必要があるため、履修する授業数が圧倒的に多くなります。
教育実習や介護実習なども必修で、教育実習も終了した今は達成感もありますが、3年まではかなり大変でした...。
通学時間が短いことで得られるメリット
私の経験を踏まえて、通学時間が短いと、以下のメリットがあると思います。
・体力の温存
朝から夜まで授業と部活で体力を使い果たしても、短時間で家に帰れるため回復が早い
・柔軟なスケジュール調整
空きコマに一度帰宅して休憩したり、忘れ物を取りに帰ったりできる
・課題に集中できる時間の確保
家でじっくり課題やレポートに取り組める
学部・学科によって変わる「忙しさのピーク」
大学生活の忙しさは、学部や取り組み方によって大きく異なります。
進路選択の際は、自分が目指す分野の「忙しさのピーク」がいつ来るかも考慮に入れましょう。
教職課程の場合
最も大変なのは2年生です。
教職関連の授業が集中し、部活動と両立するのが最も困難な時期でした。
しかし、この山場を乗り越えれば、3〜4年生では教職課程の授業はほぼなくなり、介護体験や教育実習の期間以外は、ゼミや就職活動に集中できます!
理系学部の場合
友達の話を聞くと、理系は3年以降が実験等で忙しいようです。
1〜2年生は比較的余裕があっても、3年生以降は実験やゼミ活動が本格化し、終電で帰ることが珍しくなくなります。
特に理系の実験は時間が読めないことが多く、「実験が長引いて終電を逃した」という話も珍しくありません。
文系でも油断は禁物
教養科目が多い1、2年生や、卒論執筆期間は、文系でも大学に遅くまで残ることがあります。
通学時間選びのアドバイス
もしあなたが以下に当てはまるなら、通学時間は特に慎重に検討してください。
・教育学部以外で教職課程を履修予定: 2年生の時期を無理なく乗り切れるか
・理系学部志望: 3年生以降の実験・研究活動を考慮できるか
・部活動をしたい:文化会系は大学祭前後が非常に忙しくなり、体育会系は練習や大会、合宿等で不規則になりがち。
部活やサークルは、合宿等で結構費用がかかるので、その費用を稼ぐためのアルバイトも考慮する必要があります。
理系の場合は、「1〜2年生は大丈夫だった」と油断していると、一気に負担が増える可能性があります。
だからこそ、4年間を通じて「無理なく通える距離」であることが、充実した大学生活を送るための必須条件だと思います!
最後に
今回は、「通学を重視した志望大の決め方」をご紹介しました!
進路を選ぶとき、学びたい内容や大学の知名度に加えて、「無理なく通えるか?」という点も踏まえて志望大を考えてみてくださいね!
「志望大が決まらない...」、「夏休みの勉強が進まない...」等、質問や相談などがあれば、是非、先輩ダイレクトで聞いてくださいね。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
<この記事を書いた人>
近畿大 総合社会学部 ラリマー
毎日通学で2時間歩いていますが、運動不足解消と体力向上に繋がり、自然と痩せられたのは大きなメリットです!
※この記事は、公開日時点の情報に基づいて制作しております。


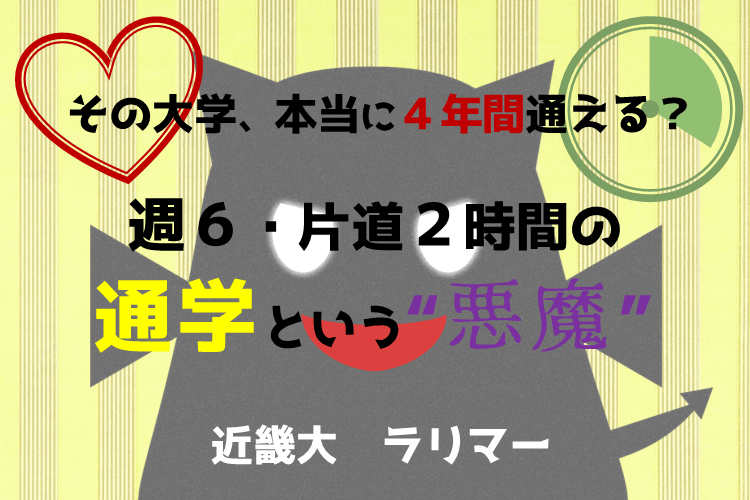





記事にコメントする
【コメント送信前に必ずお読みください】
このコメント欄では、質問や相談はできません。