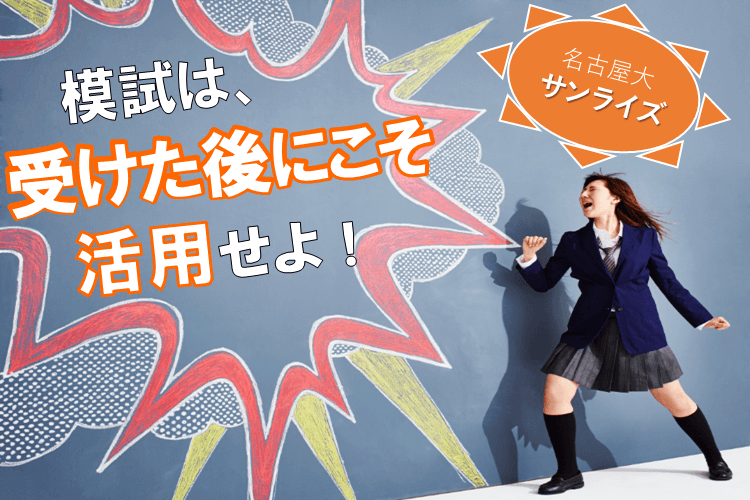
こんにちは!
名古屋大学法学部のサンライズです。
高校時代は、山岳部や書道部などいくつかの部活を掛け持ち、同時に生徒会役員としての活動もしていました。
得意教科は世界史と英語、苦手教科は数学でした。
今回もよろしくお願いします!!
この記事では、「模試をうまく活用する方法」をテーマに、僕の考えを書いていきたいと思います。
この記事を読んでいる皆さんのほとんどは、模擬試験(以下、「模試」と省略します)を既に何度も受験しているか、これから受験することを計画しているのではないでしょうか。
単に「模試の活用」と言っても、もちろん様々な方法があると思うのですが、ここでは「模試を受けた後」のことにフォーカスします(理由はこの後すぐ)!
これから模試を受験する際に、ぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。
模試は、「受験した後」の活用がカギ!!
僕の考えでは、模試は「受けた後が肝心」。
もちろん、事前に、つまり模試を受ける前に相応の対策をしてから臨んでも良いのですが、少なくとも僕自身は、事前の準備よりも「受験した後」に模試を有効活用することを、とても重視していました。
最大の理由は、僕の中で、模試は「自分の現在地を正確に、ありのままに知るための試験」だったから。
「自分の現在地」は、「志望校との距離」と言い換えても良いと思います。
僕は受験生だった頃、学校の課題など以外では「ゼミ」を中心に、つまり自習メインで学習を進めていました。
自習メインの学習は、自分のペースで勉強できるのが大きなメリットです。
ただ、どうしても「今の学習方法に足りないものは何か」「志望校の合格ラインに到達するためには、どのような勉強をするべきなのか」を、自分だけでは把握しにくいのも事実。
そんな僕にとって、模試(の結果)を活用して、その後の勉強の方針を立てることは必要不可欠でした。
勉強の計画を作ったり修正したりするには、まずは、今の自分が志望校に対してどれくらいの距離にいるのか正確に知る必要があります。
僕が模試を使って知りたかったのは、まさにその、「自分が今、志望校合格というゴールに対してどれくらいの距離にいるのか」ということ。
事前に模試に特化した対策を積んでおけば、模試そのもので良い点数を出すことはできるでしょう。
しかし、その良い点数が「本当に自分の現在地を示しているのか」は別問題。
極端な話、その時点での本当の実力を知りたければ、何も勉強しないで模試に臨んだ方が、より正確でありのままの「現在地」が分かりやすくなります。
そういうわけで、僕自身は、模試に臨むにあたっては「模試に特化した」事前の対策は最低限に留め、あくまでも普段の勉強の延長線上で受験するようにしていました。
代わりに、ここから書いていくように、模試を受けた後には、その模試を徹底的に使い倒すようにしました。
模試「受験後」の活用法①:判定を気にしない!
模試を受けた後の活用法で僕が最も重視していたこと、それは「判定を気にしない」ということ。
もちろん、判定を「気にしない」ことは、「見ない」こととは違います。
というか、どうしても、判定がどうなっているかということは気になりますよね。
僕も、友達との会話などで判定が話題になることもあったので、判定をまったく意識していなかったなどということはありません。
ただ重要なのは、判定は、「あくまでも模試を受けた時点での、模試を受けた人の中での相対的な合格可能性」でしかないということ。
言い換えれば、どんなに模試で良い判定が出ていたとしても合格は保証されないし、逆に、模試で思うような判定が出ていなくても合格の可能性はあります。
何より、判定を見て一喜一憂しても、既に受けた模試の結果を変えることはできません。
終わったこと(出た判定)を気にするよりも、これから迎える受験本番の結果をポジティブな方向に変えることに集中する方が、間違いなく得策です...!
というわけで、僕は模試の判定を「なるべく気にしない」ように、注意していました。
模試「受験後」の活用法②:自分の間違いの傾向を発見する!
僕が判定を見ることよりも意識していたのは、「自分はどんな風に間違えることが多いのか」の分析をきちんとして、具体的な勉強の方針作りに役立てること。
そもそも、僕の基本的な勉強方針は「1回目で間違えた問題を、次からは絶対に間違えないようにする」ことでした。
間違えやすい問題やミスの傾向を把握して、それに合わせて対策を積むことで、次に似たような問題に出会ったときには絶対に正解できるようにするという方針です。
もちろん、皆さん全員がこのように勉強しなければいけないということではありません。
でも、模試で間違えたときに「次には間違えないように」知識を補強したり解き方を再確認したりしていけば、必然的に、入試頻出の問題を中心に間違えることは減っていくはず。
模試の結果が返却されたら、そのような方針を効果的にするためにも、「自分はどんな問題で間違えたのか」をじっくり確認することが大切になります。
例えば、基本的な、「本来なら正解できたはず」の問題で間違えていたのなら、基本的な内容をもう一度徹底的に頭に入れ直したりケアレスミスに注意したりする必要があるでしょう。
「単語や公式さえ覚えていれば正解できた」問題ができていないのなら、そうした暗記事項に勉強時間を割く必要がありますよね。
科目ごと・分野ごとにも、そうした「間違いの傾向」および必要な対策は違ってくると思います。
いずれにしても肝心なのは、自分の間違いを把握し、「次に同じミスをしないためにはどうすれば良いか」を考え実践することではないでしょうか。
模試の結果表などをみると、各問題の正答率や「自分の偏差値帯なら正解しておきたい問題」などがまとまっていることも多いです。
そうしたデータとも比べながら、「正解すべき問題」で落としてしまっていないか・同じようなミスが重なっていないか等々、よく「自分の間違え方」を分析してみることを、強くオススメします。
模試「受験後」の活用法③:解き直しも効率よく!
さて、ここまでは模試の結果が返却されてからの「自己分析」について書いてきましたが、少し時間を巻き戻してみましょう。
模試を受けてから結果が詳しく分かるまでにも、できることがあります。
「受験したときの感覚が残っているうちに、解き直しを始める」こと。
なぜ受験したときの感覚が残っているタイミングが大事なのか。
それは、「正解の一歩手前」までいったのに正解できなかった問題が、よりハッキリ分かるからです。
例えば共通テスト形式の選択問題で、「2択まで絞ることができたけれど、決め手に欠けて一方を選んだら、正解はもう一方だった(つまり、間違えてしまった)」なんて経験、ありませんか?
こんなふうに、途中までは正しい考え方ができていて、正解できてもおかしくなかった問題は、本番までには絶対に正答できるようにしておきたいところ。
でも、そんな「2択に絞ってギリギリまで迷った」といった解いていた時のリアルな感覚は、模試を受けてから時間が空くと徐々に忘れてしまいます。
だからこそ、模試の解き直しを始めるなら、「迷った」感覚が残っているタイミングで行うべき。
模試を受けた直後なら、解答解説などを読めばすぐに、「迷ったポイントはどこか」「自分の考え方がどこまで合っていたのか」「どんな知識が足りなかったのか」といった、正答するために必要だったポイントが分かるでしょう。
僕自身、模試を受けてすぐに、とりわけ自信をもって解答できなかった問題については見直し・解き直しを始めていました。
せっかくなので、ここでもうワンポイント。
単に「模試を受けてすぐ」見直すだけでなく、それを見越して「模試の受験中から」見直したい問題をピックアップしておくのもオススメ。
解いているときに考え方に迷ったり決め手がなかったりして、「とりあえず解答したけれど、あまり自信がない」と思う問題には印をつけておき、終わった後は、それらの問題から優先的に見直し・解き直ししていくのです。
こうすることで、「解いているときに迷った問題」だけでなく、「印がついていない=確信をもって答えたのに間違えた問題」にまで、気づくことができます。
このように、模試を受けてすぐ、感覚が残っているうちに解き直しを始めることで、自分の間違いの中でも「正解できたはず」の問題に対しては、早めに対策を進められます。
さらに、模試を受けながら「今まさに迷っている問題」など見直したい問題をピックアップしておけば、より効率的に、「次は絶対に正解する」ための勉強に取り組むことができます。
見直し・解き直しは、模試を受けた後、それも「受けた直後」からコツコツ進め、効率よく苦手に絞って対策することを強くオススメします!!
まとめ:模試は、受けた後こそ活用しよう!
以上が僕の、「模試を受けた後の活用法」です。
もちろん、究極的には人それぞれのやり方で活用すれば良いのですが、どうせなら模試(の結果)から1つでも多くの収穫を得て、受験本番の結果を良いものにしたいですよね。
判定を気にするのは、志望校の最終決定など重大な局面だけで十分だと、個人的には思います。
それよりも、勉強の計画作りや計画修正に直接役立つ情報を模試からたくさん手に入れて、ミスを少しでも減らす方向で勉強していくことを、強くオススメします。
「進研模試対応 大学合格逆算ナビ」でキミの合格への伸びしろを発見しよう!
進研模試 大学入学共通テスト模試・6月の結果は7/9(水)受付開始!
「進研模試対応大学合格逆算ナビ」提出はコチラから
※進研模試に対応。
※受講科目にかかわらず利用可能。
※「キミ専用模試復習プログラム」は提出後すぐに利用可。 「合格戦略書」は提出いただいた方へ、模試回ごとの配信開始日以降にPDF配信。配信開始日以降は、受付後約7日(日・祝・年末年始を除く)でお届け。
※進研模試の受験予定がない方は「合格戦略アドバイス」 (「サクセスページ」または「会員ページ」の「質問・相談」からアクセス)で模試結果を踏まえた進路・学習法相談ができます。
※ 「SASSI」で始まるIDは、ベネッセのテストの成績表のログインIDまたは学校で配られるログインカードに記載されています。わからない場合は、学校の先生にご確認ください。
<この記事を書いた人>
名古屋大・サンライズ
ひとこと:暑い日が続きますね。体調管理も立派な受験対策なので、熱中症や夏バテには要注意!体調第一で、心身ともに集中して勉強できる環境を作りましょう。
※この記事は、公開日時点の情報に基づいて制作しております。


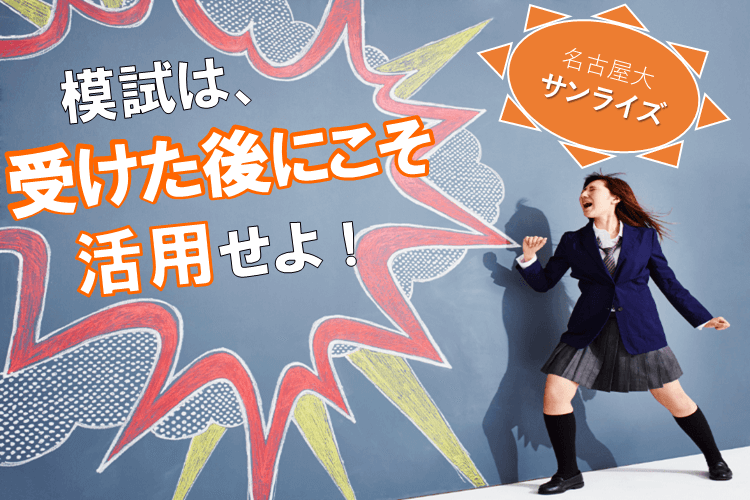





記事にコメントする
【コメント送信前に必ずお読みください】
このコメント欄では、質問や相談はできません。