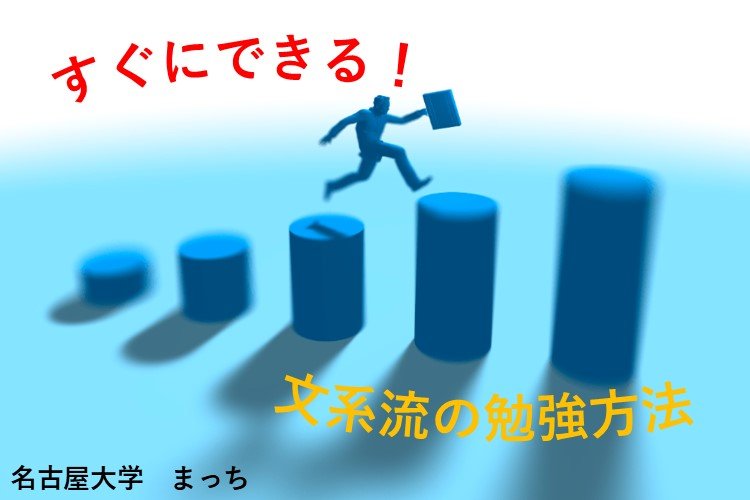
皆さん、こんにちは!
名古屋大学のまっちです。
2年生になって、学校によってはもう文系と理系に分かれている方も少なくないと思います。
勉強する科目も文系と理系で変わり、勉強方法について悩む方もいるのではないでしょうか。
そこで、文系流の勉強方法と題して、私が実際にやっていた文系ならではの勉強方法についてお伝えしたいと思います。
参考になれば幸いです!
①インプットは早めに取り掛かる!
文系の科目の特徴として、理系科目よりも暗記しなければならないこと、覚えなければならないことが多いということがあります。
受験の二次試験で国語を使う場合には古文単語をしっかり覚える必要がありますし、社会科目で地理以外を選択する場合には膨大な量の暗記が必要になると思います。
勉強となると、問題を解くことが大切だと考える方も多いかもしれませんが、十分にインプットができていないまま問題を解いても、余計にわからなくなってしまう可能性があります。
なので、受験はまだまだ先だとは思いますが、定期テスト対策の勉強をするときでも、できるだけ早い段階からインプットだけしておくと、余裕をもって勉強を進められると思うのでおすすめです!
私は世界史と倫理・政治・経済を選択していたので、この科目だけはテスト週間が始まるよりも1週間程度前からインプットを始めていました。
これのおかげで、テスト週間は数学や英語なども含めてバランスよく勉強できたので、いつも一夜漬けになってしまう人はぜひやってみてくださいね。
②アウトプットはほどほどに!
教科書やプリントを見返して一通りインプットを終えたら次は問題を解いてアウトプット...なのですが、ここで一つポイントがあります。
それは、アウトプットはそんなにやらなくても大丈夫だということです。
もちろん、まったくやらないのではインプットした知識を使うことができないのである程度はやらなければなりません。
しかし、覚えることが少なくて演習量が大事になる数学などの理系科目とは違い、文系科目はそこまで演習をしなくても、しっかりインプットができていれば大丈夫だと思っています。
実際、私は社会科目については、テスト勉強のときは問題を解いたことはありませんし、受験勉強のときでもほとんど問題の解答を書いたことはありませんでしたが、特に問題はなかったので、あまりアウトプットは必要ないと思っています!
まとめ
ここまで読んでくれてありがとうございます!
今回は、インプットとアウトプットの二つの観点から、文系ならではの勉強方法についてお伝えしました。
もう文系に進んだ方も、まだ決まっていない方も、ぜひ参考にしてみてください!
<この記事を書いた人>
名古屋大学 まっち
※この記事は、公開日時点の情報に基づいて制作しております。








記事にコメントする
【コメント送信前に必ずお読みください】
このコメント欄では、質問や相談はできません。