
こんにちは!
立命館大学情報理工学部の霜月です。
僕は日本史が一番得意という文系脳でありながら、理系である情報理工学部に進学しています。
そんな僕から、今回は文系と理系の「頭の使い方」の違いについて紹介したいと思います!
何を理解して、何を習得するのか
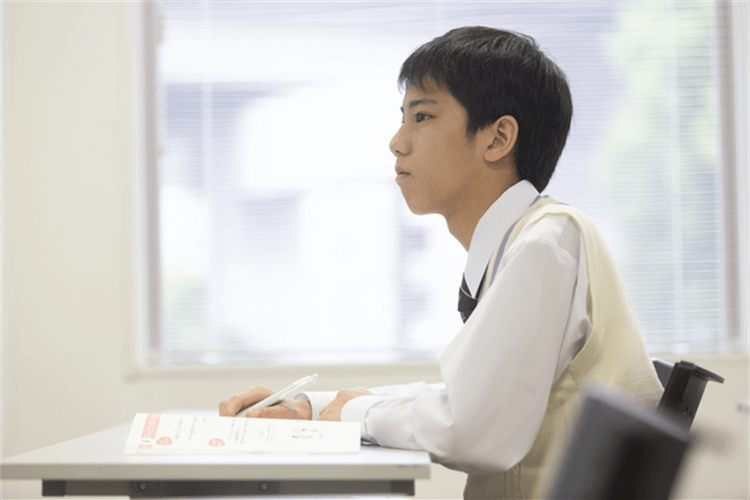
文系と理系の勉強法の最も根本的な違いは、「何を理解し、何を習得するか」という点に集約されると私は考えます。
文系科目は、歴史の流れ、社会の仕組み、人間の心理など、多岐にわたる概念や事象を深く理解し、それを多角的に捉えることが求められます。
例えば、歴史であれば単なる年号や事件の暗記に留まらず、その背景にある思想や社会情勢、そしてそれが現代に与える影響までを考察する力が必要です。
一方、理系科目は、物理法則、数学の定理、化学反応など、明確なルールに基づいた論理を構築し、それを問題解決に応用する能力が重視されます。
公式を覚え、それをいかに正確かつ効率的に適用できるかが問われるのです。
理系ならではの勉強法:演習と試行錯誤による定着

理系の勉強法は、「演習と試行錯誤」が核となります。
数学や物理、化学といった科目は、インプットした知識をアウトプットする練習が不可欠です。
問題集を繰り返し解き、間違えた問題はなぜ間違えたのかを徹底的に分析する。
このプロセスを通じて、公式や定理の理解を深め、応用力を高めていきます。
例えば、物理であれば、ただ公式を暗記するだけでなく、それがどのような物理現象を表しているのかをイメージし、様々な状況でどのように適用されるのかを演習を通して体得します。
実験を通して理論と実践を結びつけることも、理系ならではの非常に有効な学習法です。
何度も手を動かし、試行錯誤を繰り返すことで、抽象的な概念が具体的な形となり、理解がより強固なものになります。
文系ならではの勉強法:多角的な情報整理と論理的思考の深化
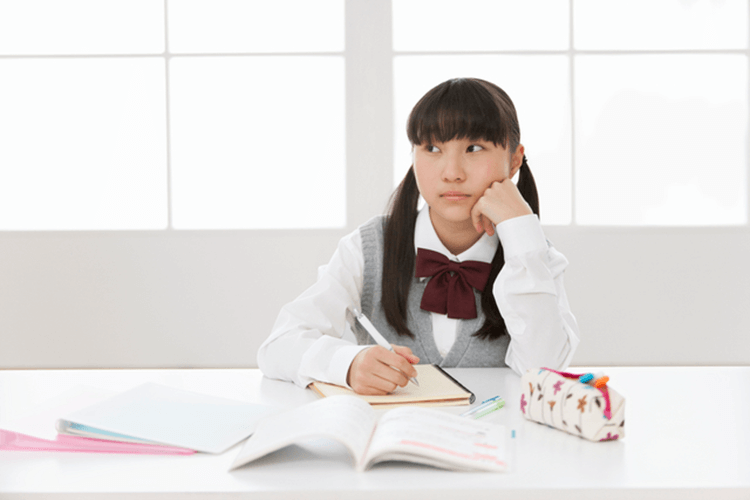
一方、文系科目の学習では、「多角的な情報整理と論理的思考の深化」が重要になります。
歴史や地理、政治経済、現代文など、情報量が非常に多いのが文系科目の特徴です。
これらの情報を単に暗記するのではなく、それぞれの事象がどのように関連し合っているのか、どのような背景を持っているのかを体系的に理解する必要があります。
例えば、歴史であれば、年表を作成するだけでなく、その時代の文化や経済、人々の生活様式などを多角的に捉え、なぜそのような出来事が起こったのかを論理的に考察する。
現代文であれば、筆者の主張を正確に読み取り、その論理構造を把握し、自分の言葉で要約したり、意見を述べたりする力が求められます。
単語帳や用語集の活用はもちろん有効ですが、それらを活用しつつ、異なる情報源を結びつけ、自分なりの解釈や考察を加えることが、文系科目における深い学びに繋がるでしょう。
まとめ
文系と理系の勉強法は一見すると大きく異なるように思えますが、その根底には共通して「本質的な理解」を追求するという目的があります。
理系は論理を組み立てることで事象の本質を捉え、文系は多角的な視点から概念の本質を深く掘り下げます。
どちらの分野に進むにしても、ただ知識を詰め込むだけでなく、なぜそうなるのか、その意味は何なのかという「問い」を持ち続けることが、真の学びに繋がるのではないでしょうか。
理系の私から見ても、文系の皆さんの思考の深さや、多岐にわたる情報を統合する能力は、非常に魅力的であり、学ぶべき点が多いと感じています。
今回はミライ科の記事ということでまとめましたが、書ききれていないことがたくさんありますので、気になった方はぜひ先輩ダイレクトから先輩に聞いてみてください!
自分が志望する大学の先輩を指名して質問すれば、より近い回答が得られること間違いなし!
それではまた!
<この記事を書いた人>
立命館大 霜月
※この記事は、公開日時点の情報に基づいて制作しております。







記事にコメントする
【コメント送信前に必ずお読みください】
このコメント欄では、質問や相談はできません。