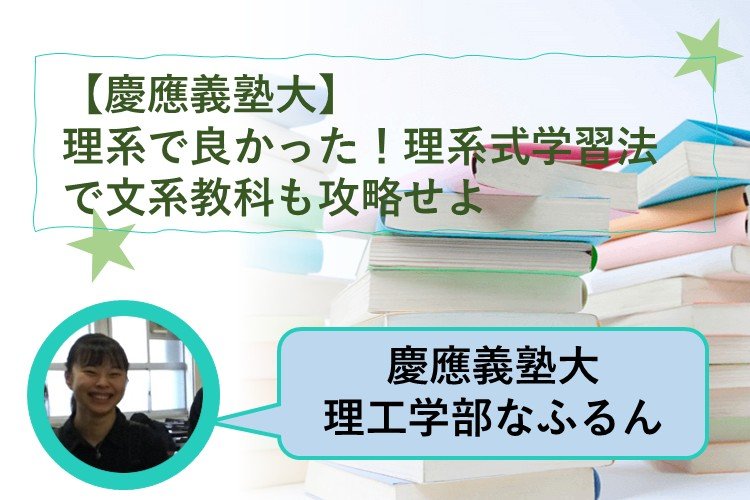
こんにちは。
慶応義塾大のなふるんです。
夏も盛りの時期に近づき、あと1か月で夏休み!というところですね。
文理選択後ちょうど2か月が経ったという人も多いかと思いますが、皆さんの今の学習内容に対しての印象はどのようなものでしょうか。
理系に入って良かったと思っている人もいれば、こんなはずじゃなかった...という人もいるかもしれません。
文系と理系という区分は、高校も後半になってくると内容の違いによりさらにはっきりと感じられる大きな仕切りのようなものです。
違いがたくさんあるにも関わらず、英語も国語も社会も...と、入試や普段の授業では文系の教科も取る必要があるのは本当に難しいところですよね。
今回の記事では、理系と文系の勉強方法の面での違いを超えて学習するためにはどうすればよいのかを書いてみたいと思います。
ポイントは2つ、
・文系教科も証明のように変換!
・理系教科の特徴を生かすには?
です!
理系で満足している人も、困っている人も、よかったら最後まで読んでみてくださいね!
① 【文系教科を全部証明に変換!?】
理系の目玉ともいえる証明。
記述問題はもちろん文系にもたくさんありますが、理系の数学、物理や化学の証明との相違点は、いろいろな分野の内容を様々な順序、角度から拾う必要がある事、時に多くの証明の仕方をもつこと等だと思います。
これを文系教科に応用できないか?と考えてみました。
国語:選択問題も記述と思って追っていこう!
記述式の国語を入試で使う予定の人にとっても、共通テストでのみ国語を使う人にとっても、思考の過程を言語化するという勉強方法はとても有用です。
全部の問題に対して書き出すのはなかなか大変かもしれませんが、迷った問題について最終的にその答えを導いた理由を、頭の中だけではなく実際に書いてみるのはおすすめです。
例えば...
・何段落に、○○と書いてあった。(この段落の内容は主に××である)
・次の段落には△という例が出ていた。(前の段落とのつながりは□□)
これらのことから、△は、○○の狭義での例であると考えられたので、この△の抽象的な説明を用いて、~~のように...。
といったようにすると、解説の手順とどこが違うのか、別の考え方はないのか、などといったことが見えやすくなりますよ!
社会:自分で一から説明を組み立てる!?
単語を覚えたり、用語の意味を正確に理解したりすることができたら、こちらも証明のように組み立て作業をすると、社会の学習も進むかもしれません。
つまり、分野を細かく分けて、思いついたキーワードをピックアップ、その後、その分野について、選んだ言葉を用いて簡潔にまとめるということを繰り返すというものです。
単語や概念の定着率が上がるうえ、全体像が見えやすくなると思います。
分野を分けるときには、例えば地理なら
△地誌、アフリカ大陸
◎地誌、アフリカ大陸北部、気候について
など、できるだけ細かくすることで説明もしやすくなり、後々他分野との組み合わせでもこのような学習法が使えるようになると思います。
英語:記述に変換、他教科への興味と相性◎
ここに関しても、まずは国語と同様の学習ができると思います。
自分の解答がどうして導きだされたのかということを確認してみるとよい学習になるはずです。
また、英語に関しては他にも理系であることを生かせる学習方法があります!
それは、自分の興味のある理系科目の内容を取り扱っている文章などを読んでみることです。
もちろん専門的すぎると難しくてかえって読みにくいとは思うのですが、入試問題になっている程度の新しい分野に触れられるタイプの文章などであれば、比較的楽に取り掛かれるのではないかと思います。
私は、他大学の入試問題でそのような素材を見つけることで、英語の学習の面白さを再確認していました。
② 【理系教科は区切りやすい!?】
もちろん文系にも大論述などとても時間のかかる問題はあるとは思うのですが、理系のための理系教科というものは、解答を書き始める前から時間がかかって仕方のない問題が多いですよね。
定期テスト前など、英語や国語もやらなければいけないのに、理系教科に阻まれてなかなか手が付けられないということもあるとかもしれません。
それを未然に防ぐためにおすすめしたいのが...
毎日、その日の授業までの知識を使って解ける問題を解くことで積み重ねを作るということです。
社会や英語の問題と異なり、理科や数学は分野融合問題でなくとも記述力を試すことのできる問題を多くもっていることが特徴だと思います。
そういった特徴を生かして、公式や言葉の確認にとどまらず、重みのある問題を1問でも解いていってみるということが割と効果的なこともあるんです!
私は1,2年生の頃、まだ難しそうだから基礎的な問題を週末に解いてから来週に...という先延ばしの癖があったのですが、3年生になってから改めて見てみると、日々解いておけばよかった!と思うものも多くありました。
・教科書傍用参考書の発展問題
・教科書の章末問題
・進研ゼミの証明問題
など一日少しでも解けそうなものにチャレンジしてみるのがおすすめです。
ここまで、理系教科と、理系の特徴について、さらにそれを生かした学習法について書いてみました。
2年生という学年はまだまだ試行錯誤で自分のスタイルを確立していく過程だと思うので、焦らなくても自分の「ペースで」進めていけば大丈夫です。
自分に合った方法が見つからないなど迷っている人にとって、この記事が少しでも役に立ったらうれしいです。
頑張る皆さんのことを心から応援しています!
<この記事を書いた人>
慶應義塾大 なふるん
今月は今まで乗ったことのない電車の路線を開拓する機会があり、わくわくしています。
※この記事は、公開日時点の情報に基づいて制作しております。


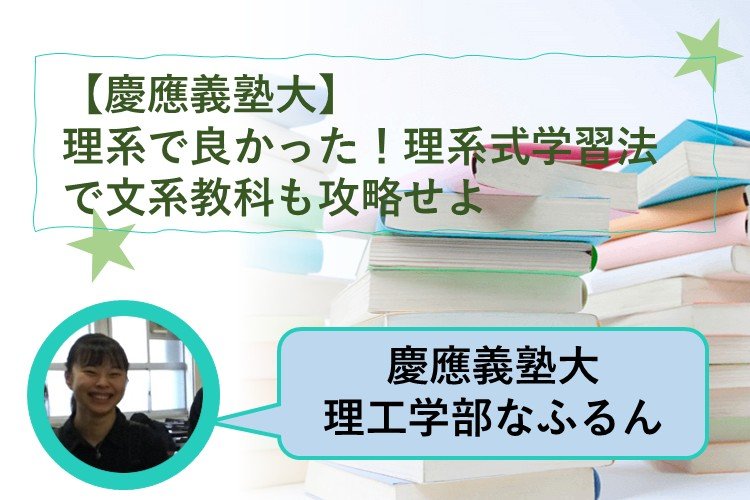





記事にコメントする
【コメント送信前に必ずお読みください】
このコメント欄では、質問や相談はできません。