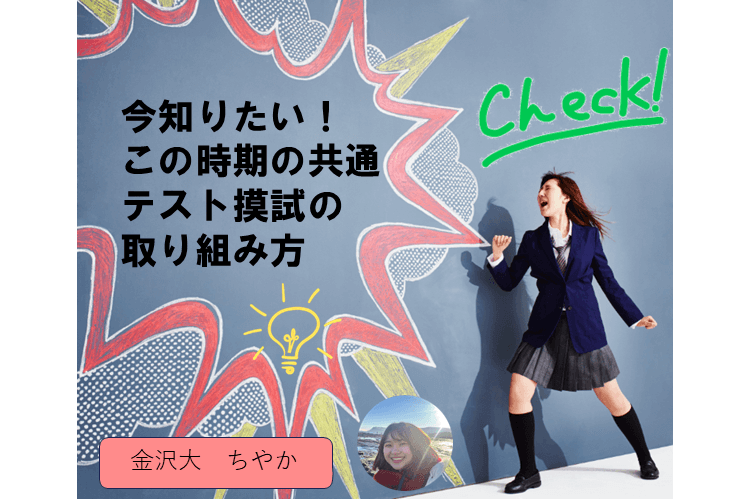
みなさんこんにちは、金沢大学のちやかです。
桜の季節が終わり、新緑がまぶしいこの頃。5月の涼しい風が心地よく感じられますね。
高3になって摸試の回数が増えたと感じていませんか?
次々とやってくる摸試。その種類は大きく分けて
①共通テスト摸試
②個別試験対策摸試
の2つに分けられるかと思います。
今回は、高3の今の時期における①の共通テスト摸試の向き合い方についてお伝えしていきますね!
解いて終わりではなく「見直し」までが摸試
さて、なぜ受験生は毎月のように摸試を受けるのか。
それは本番の環境に慣れるためであり、自分の苦手を洗い出すためでもあります。
普段は解ける問題でも、白紙の状態で時間制限がある中で、自分の力だけで解けるのか問われているのが摸試なんです。
摸試で間違えた問題は必ずその原因を分析して、何を理解すれば次は解けるだろうか、ということを明確にしましょう。
今の実力を「客観的に」把握する
高3の5月は、本格的に受験勉強に取り組む人が多くなる時期です。
そんな中で、全国で見た自分の立ち位置を知ることで、目標まであとどれくらいなのか客観的に把握することができます。
そして、本番までに何をどれだけ取り組むか逆算して勉強計画を立てることが可能になりますよ。
摸試は時間配分を計算する練習
何度も言いますが、摸試は「練習試合」です。
そして、本番に近い形式で出されるので、試験のときにどの問題から解くか、問題を何分で解くか、といった自分なりの戦略を立てることができます。
それを毎回の摸試で行うことで、自分が一番いいパフォーマンスができる問題の解き方を実践できるので、一回一回の摸試を大切にしてくださいね。
さいごに
今日は、高3・5月の共通テスト摸試の取り組み方についてお伝えしました。
これから夏に向けて、まだまだ伸びしろはたくさんなので、せっかく摸試を受けるなら、「受けて終わり」ではなく「次につなげる」使い方を意識してくださいね!
応援しています!
<この記事を書いた人>
金沢大学理工学域 ちやか
みなさんはお花見をしましたか?私は花より団子派です(笑)
※この記事は、公開日時点の情報に基づいて制作しております。


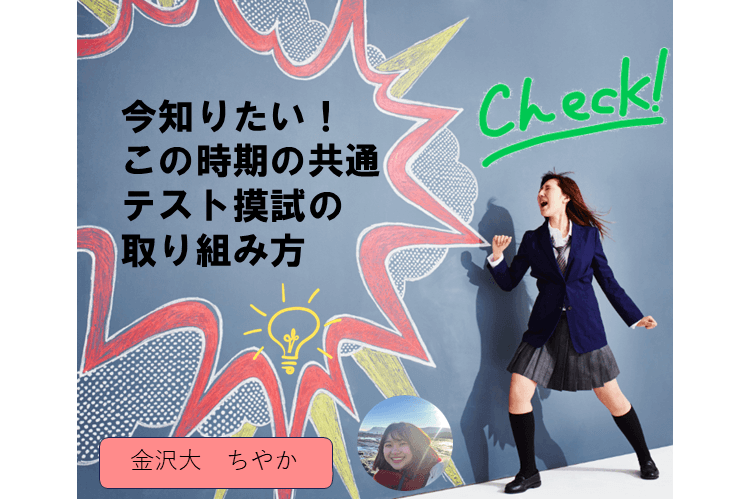





記事にコメントする
【コメント送信前に必ずお読みください】
このコメント欄では、質問や相談はできません。