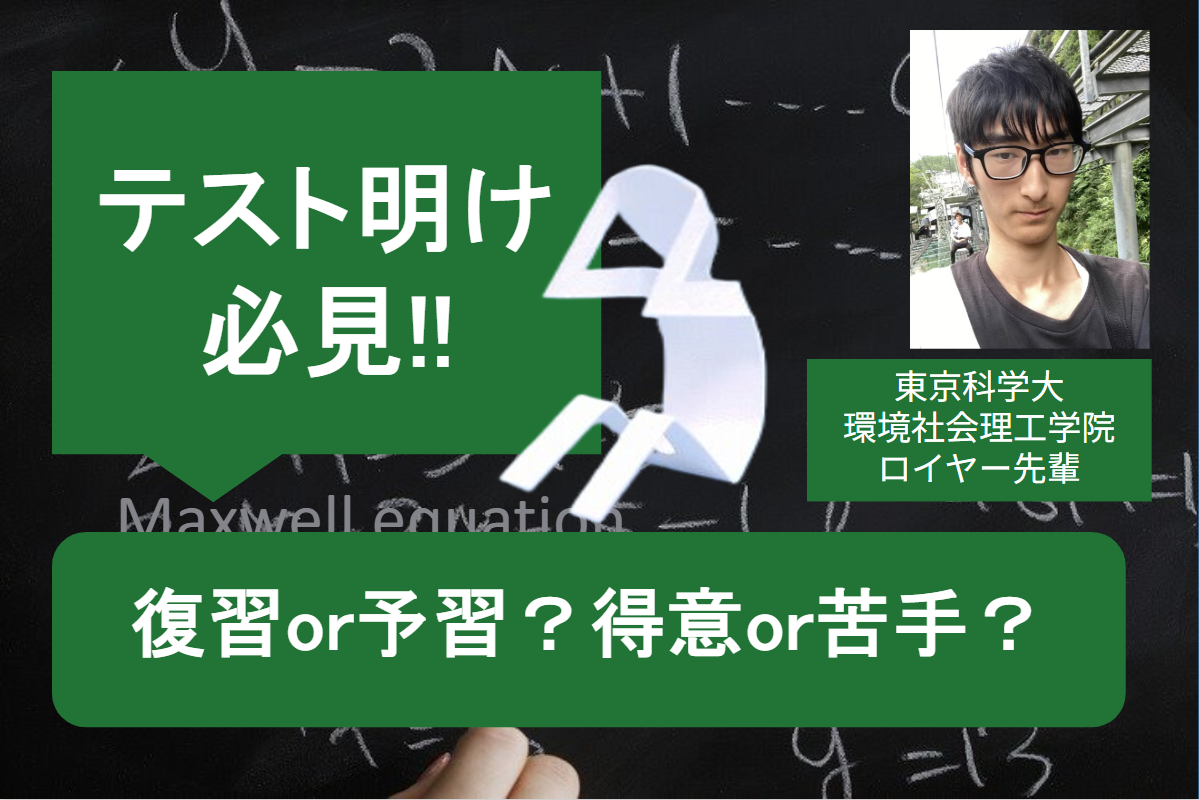
こんにちは!
東京科学大学理工学系環境社会理工学院のロイヤーです!
2年生になって初めての定期テストの範囲がわかって、もう直前だったり終わってたり。
テスト明けにこんなことを思ったことがある人、また今Right nowで悩んでいる人もいるのではないでしょうか。
「次のテストこそいい点とれるように予習したいけど、今回の範囲の復習もしないと...」
「得意な科目を伸ばしたほうがいいのか、苦手な科目の穴埋めをしたほうがいいのか...」
そこで今回は、予習と復習をどっちを先にやったほうがいいのかや、得意科目と苦手科目の順番について説明していきます。
繋がりを意識した復習が最初
結論を述べるなら、まず最初は復習です。
ただ大事なのはただ問題を解き直したり、教科書を読むことではありません。
一番最初にやるべきなのは、何がわかっていないのかがわかることです。
自分は高2の時に2年の力学を解いたら基礎が解けて基礎なしが解けない、演習不足だと思い勉強していました。
実は1年の力の向きとかがわからなかったことが判明したのは高3の秋、本格的に入試演習してた頃。
皆さんはこうならないように、わからないところをドンドン穴埋めしていきましょう。
今回のテストどこがわからなかったのか、逆に何がわかれば点を取れたのかを早いとこ復習しておきましょう。
また予習も同様です。
大切なのは、どの分野から派生してきたのかを意識することです。
まず手を付けるのは苦手科目
苦手科目が苦手なのは、苦手だから勉強も手をつけにくいからなのかなと思います。
しかも、苦手だから手も止まりやすく集中も続かない。
自分は物理の新しい分野の最初だけ勢いがあるのに、わからないのでどんどん勢いがなくなって手が進まなくなるということを何度も繰り返していました。
そのため、とにかく勉強をするときは苦手科目を最初に手を付けて、ガス欠になってきたら得意科目で息抜き。
一息ついたらもうワンプッシュ。
飴と鞭というか、得意科目を目標にして苦手科目を走り抜けてました。
人参吊り下げた馬みたいな感じですね。
まとめ
①繋がりを意識した復習が最初
②まず手をつけるのはニガテ科目
その勉強法の悩み、自分と似た先輩のアドバイスで解消しよう!
高2が始まってはや2か月。
授業スピードは一気に上がり、内容も難しくなったと感じているなら勉強法を見直すチャンスです!
そして、自分のトクイ・ニガテ、学習スタイルによりあった勉強法が知れるとうれしいですよね。
そこで役立ててほしいのが「文理別学習法データベース」。
全国の約150大学の先輩たちの合格につながる体験談がたくさん詰まった場所です。
データベースを使うときは、「自分に似たコーチを探す」機能がおすすめ。
文理、得意科目、苦手科目、さらには部活、学習スタイルから、自分に合う先輩に絞ってアドバイスを見ることができますよ!
文理別学習法データベースには、たくさんの先輩の経験が詰まっているので是非参考にしてください。
<この記事を書いた人>
東京科学大 ロイヤー
サムネのマクスウェル方程式には気づいてもらえたでしょうか...。
※この記事は、公開日時点の情報に基づいて制作しております。


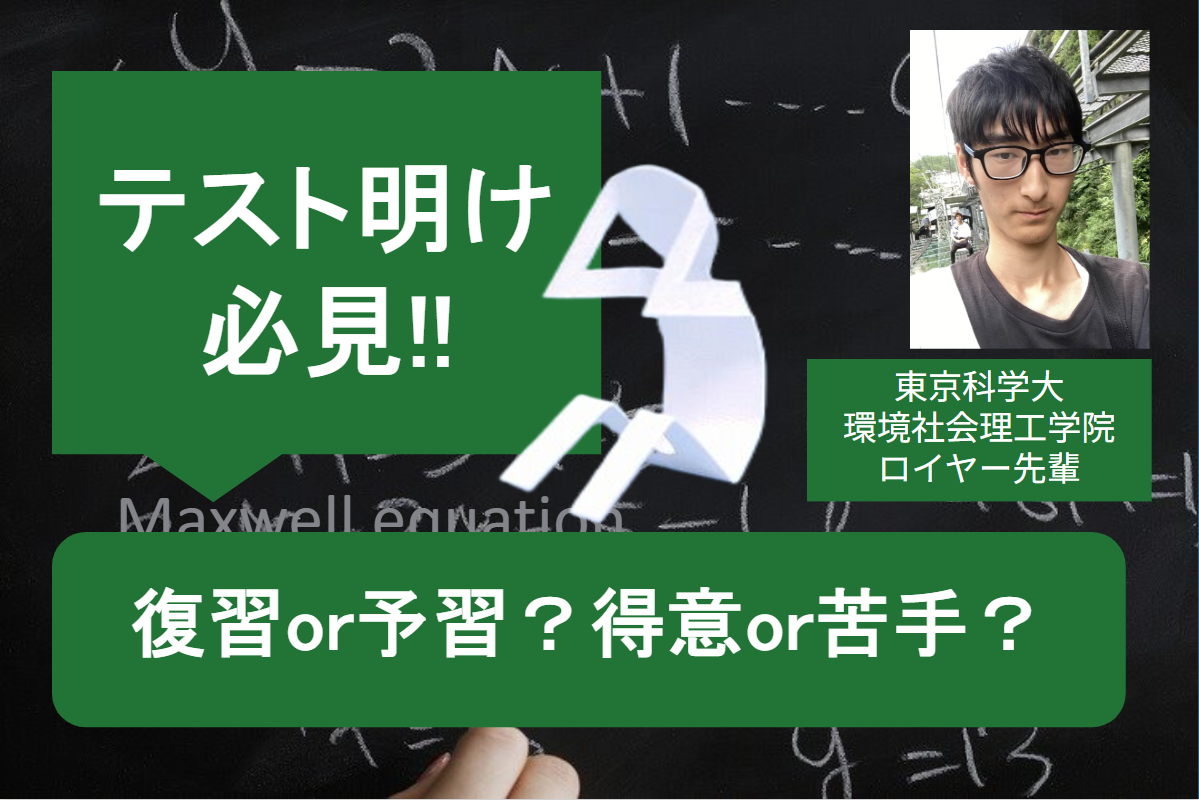





記事にコメントする
【コメント送信前に必ずお読みください】
このコメント欄では、質問や相談はできません。