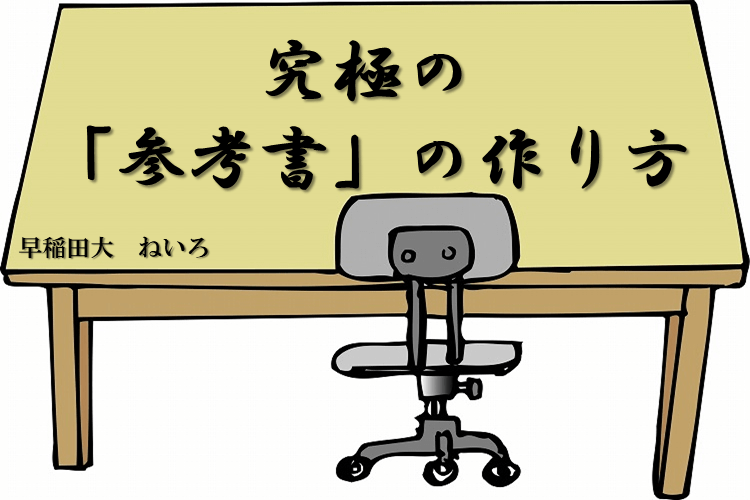
こんにちは、早稲田大学のねいろです!
いよいよ新学年、高3。
つまり受験生の年が始まりましたね。気合い入ってますか!?
今回は、そんな「高3」のみなさんに向けて、私が実際にやっていた"受験に役立つノートの使い方"を紹介します!
① ノートは"まとめる"ためじゃなく、"点を取る"ためのもの!
高3になると、多くの授業が「知識を習う」から「問題演習中心」に変わりますよね。
私の高校でも、国・数・英・理の授業はとにかく演習重視 (日本史世界史は普通に講義でした)!
だから私は、授業の前に問題を自分で解いておくようにしていました。
そして授業中は、
・解き方の別パターン(別解)をその場で追記
・先生の言った「ミスしやすいポイント」を横にメモ
・自分の解き方と比べてどこが速かったか・正確だったかをチェック
このやり方で、ノートが「自分専用の攻略メモ」になっていったんです。
ノートを見れば、自分がどこでつまずきやすいか、どんな出題で注意すべきかがすぐわかる。
ただ板書を写すだけじゃ、正直もったいないです!
② 世界史は"色×ページ番号"で記憶に残す!
社会(特に世界史)はとにかくカタカナが多すぎる!!
「えっこれ人の名前?国の名前?事件?」ってなること、ありますよね(え、ない?あるよね...?!)
そこで私がやっていたのは、
・人名=赤、国名=青、出来事=緑で色分けして、ぱっと見で種類がわかるようにする
・ノートやプリントに書くときは、「教科書P.○」って必ずメモしておく
こうしておけば、復習するときに「どこに書いてあったっけ?」と探し回らなくて済みます。
記述問題や論述問題でも、「あのあたりの流れをまとめて覚えてた!」って引き出せるようになりました。
③ ノートより"教科書メモ"!手間をかけずに超効率化
とはいえ、高3ってほんとに時間が足りない。
ノートを作り込んでたら、「あれ、今日ほとんど勉強進んでない...」ってこともザラにあります。
私がたどり着いた答えは、
最悪、ノートなんてなくてもいい。教科書さえあればなんとかなる!
具体的には、教科書の空きスペースに直接メモを書き込むスタイルに切り替えました。
・授業中、先生の話を聞きながらそのまま教科書に書き込む
・自分の言葉でポイントを整理して、過去問で出たところにはマークをつけておく
・色分けも使って、見やすさをキープ!
これなら、復習のときに教科書だけ見ればOK!
過去問を解いたあとも、「この単元で出たんだ!」って印をつけておけば、直前期の見直しが超ラクになります。
教科書を"究極の自作参考書"に育てていく感覚で使ってました。
最後に
「使えるノート」は人それぞれ。でも目的はひとつ。
ここまでいろいろ紹介してきましたが、どんなノートの使い方でも一番大事なのは「受験で点を取るため」に使えているかどうか。
・人と違う解き方や視点を残しておく
・忘れそうな情報を色やページとセットで記憶する
・ノートを頑張りすぎない!むしろ教科書と一体化させる
これらを意識するだけで、ノートがただの紙から"合格への武器"になります。
ぜひ、自分に合ったスタイルで「受験に使えるノート」、作ってみてくださいね!
<この記事を書いた人>
早稲田大 ねいろ
ゼミの初回発表が近づいてきて緊張しまくりです...
※この記事は、公開日時点の情報に基づいて制作しております。








記事にコメントする
【コメント送信前に必ずお読みください】
このコメント欄では、質問や相談はできません。