皆さん、こんにちは!
近畿大のラリマーです!
受検勉強や中間テスト勉強が上手く進んだ人もそうでない人も、気持ちを切り替えて、引き続き勉強を頑張っていきましょうね!
そして、授業や勉強で、ノートを使う人が多いと思いますが、ノートを上手く使い分けていますか?
なんとなくノートを使って、後で書いた内容がわからなくなった経験がある人も多いと思います。
そこで今回は、「シンプルでわかりやすいノートの作り方」をご紹介します!
この記事を参考にしながら、自分なりに使いやすいノートの取り方を考えてみてくださいね!
3種類のノートに分けて使おう!
1冊のノートに全ての内容を書こうとすると、莫大なページ数になります。
そして、後で見直しをしたい所を探すのが大変で、時間のロスができてしまいます...。
一方で、細かく分けすぎると、目的ごとにノートを変えるのが大変になってしまいます...。
そのため、ノートは科目それぞれ"3冊ずつ"用意して使い分けるのがおすすめです!
私は、各科目「授業用ノート」、「問題を解くためのノート」、「覚えるためのノート」の3種類で使い分けていました!
以下で、それぞれのノートの使い方を紹介します!
授業用ノート
ノートの使い方
このノートは、授業を聞いて、「板書を取ったり、先生の話のメモを取ったりするため」に使います!
授業プリントが配られている場合は、ノートは作らず、プリントに書き込んだ方がよりわかりやすくメモが取れると思います!
書く時のポイント
授業は、ゆっくり書いていると間に合わなくなるので、聞こえてきたものを箇条書きで書くのがおすすめです!
板書がある場合は、板書の一部の用語に線・矢印を書いた上で、"青色"で先生が話した内容のメモや疑問に思ったこと等を書いていました!
そして、授業後に見直せるように、先生がポイントと言った所や、授業中に何度も言っていた所などの、「重要な部分」は赤色で書いたり、波線を引いたりすると、より見直しやすくなります。
問題を解くためのノート
ノートの使い方
このノートは、学校や家で「問題集などの問題を解くため」に使います!
問題を解いたら、見直しをすることがないため、使い終わって置き場所に困ったら、捨てても大丈夫です!
ノートを用意するのが面倒であれば、広告や捨てる予定のプリントの裏紙、コピー用紙等でも大丈夫です!
書く時のポイント
全ての問題を書いて解くと、かなり時間がかかってしまいます...。
過去問や模試を解く時は、問題を解くスピードを上げるためにきちんと書いて解きましょう。
ただ、問題集などで問題の解き方を身に着けたい時は、書いて解く問題と書かずに解く問題を分けるのがおすすめです!
私の場合は、以下のようにノートに書いて解くか決めていました!
<数学や理科の計算問題>
・問題を見て解き方が完璧にわかる場合:書かずに次の問題に移る
・問題を見て解き方がわからない場合:ノートに書いて解き、解けない場合は問題に印をつける
<理科や社会の用語問題>
・1回目:漢字やカタカナを完璧に書けるか見るため、書いて解く
・2回目以降:書かずに答えを声に出して言い、間違えていた場合は問題に印をつける
<英語や国語の文章問題>
・書きながら考えることが多いため、全て書いて解く
このように、問題を解く時は、"ノートに書いて解く問題"、"ノートに書かずに解く問題"を分けるのがおすすめです!
過去問を使った勉強方法は、以下の記事で詳しく紹介しています!
覚えるためのノート
ノートの使い方
このノートは、問題を解いた後、「覚えるべき内容をまとめるため」に使います!
隙間時間や寝る前などに、このノートを何度も見直すことで、効率良く苦手克服ができます!
書く時のポイント
英語や国語は復習が難しいですが、このノートに"本文や問題で出てきた、わからない単語や文法を書く"のがおすすめです!
そうすると、このノートを見るだけで問題の復習ができ、復習の効率が上がります!
また、このノートでは、覚えるべき所を暗記用ペンで書いて、赤シートで隠しながら確認できるようにすると良いと思います!
付箋に覚えたい内容を書いて、確認した時に覚えていたら付箋にチェックをつけ、3~5個チェックが付いたら剥がすようにすると、覚えた時に達成感を感じやすくなります!
私は、付箋に英単語を書いて、1日後、2日後、3日後、1週間後、1か月後の5回チェックがついたものは剥がすことを繰り返していました!
最後に
今回は、「シンプルでわかりやすいノートの作り方」をご紹介しました!
この記事を参考にしながら、自分なりに使いやすいノートの作り方を考えてみてくださいね!
「部活と受験勉強の両立が大変...」、「受験勉強と中間テスト勉強の比率がわからない...」等、質問や相談等があれば、ぜひ、先輩ダイレクトで聞いてくださいね。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!
<この記事を書いた人>
近畿大 総合社会学部 ラリマー
模試や受験を受ける時は、覚えるためのノート、単語帳、暗記BOOKをいつも持って行っていました!
※この記事は、公開日時点の情報に基づいて制作しております。


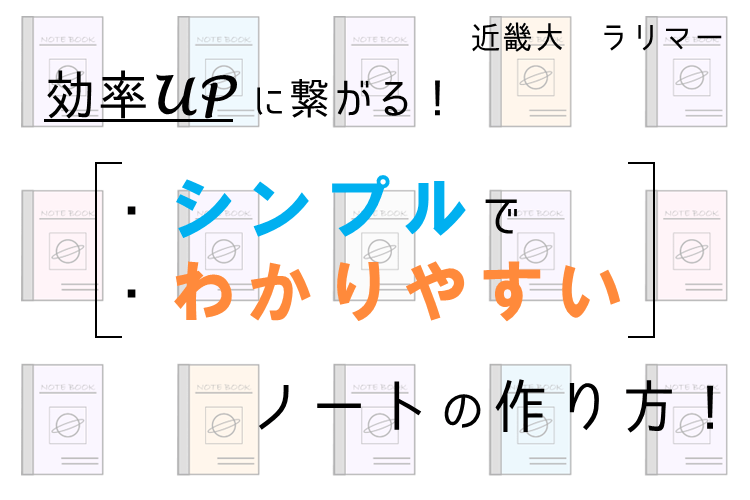





記事にコメントする
【コメント送信前に必ずお読みください】
このコメント欄では、質問や相談はできません。