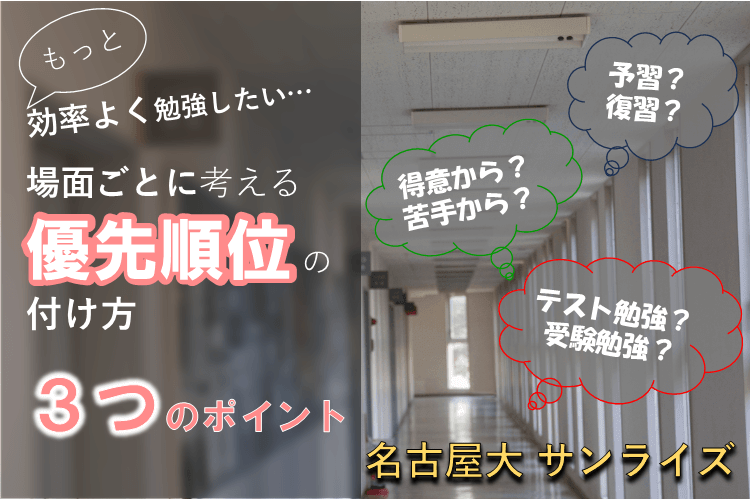
こんにちは!
名古屋大学法学部のサンライズです。
高校時代は、山岳部や書道部などいくつかの部活を掛け持ち、同時に生徒会役員としての活動もしていました。
得意教科は世界史と英語、苦手教科は数学です。
今回もよろしくお願いします!!
この記事のテーマは、「勉強するときの、優先順位のつけ方」です。
勉強をしていると誰しも、多かれ少なかれ「どれから手をつけよう?」とか「試験勉強したいのに、課題が終わらない...」とか、悩むこともあるでしょう。
もちろん、「やりたいと思ったこと」全部に取り組めたらベストですが、そんな余裕はなかなか作れないのが実際のところですよね。
ここでは、そんなお悩みが生まれやすい3つの場面を想定して、「こんなふうに優先順位をつけてみたら効率よく勉強できるかも!」と僕が考える「優先順位のつけ方」をご紹介します。
参考にしてもらえたらうれしいです!!
場面1:得意から?苦手から?
最初は、「得意教科から勉強するか、それとも苦手教科から進めるか?」考えてみたいと思います。
結論だけ言ってしまうと、僕は「苦手なものに多くの時間を割く」ことにしていました。
皆さんは、得意な教科と苦手な教科の勉強が選べたら、どちらを選ぶでしょうか?
僕は、何の制約もなければ、まず間違いなく得意な教科を選んでしまいます。
しかも、ダラダラと得意な教科の勉強ばかり続けてしまうと思います。
①「見切りをつける」ことの重要さ
「いやいや、別に得意教科を先にやっても、後で苦手な教科もやればよいでしょ」...?
たしかにそうかもしれないけれど、ちょっと待った。
得意な教科を"ほどほど"で切り上げて、苦手な教科の勉強を新たにスタートできるでしょうか。
少なくとも僕は、絶対に無理ですね...(苦笑)。
得意な教科は自分にとっても楽でサクサク進められますが、苦手教科はそうはいきません。
そうでなくても苦手な教科の勉強を、得意な教科の勉強を中断してまで進めるのは、どんなに「やらなきゃ」と思っていても大変なこと。
ただ、言うまでもないことですが、いつまでも得意な教科の勉強ばかりしていては、苦手な教科がますます疎かになってしまいます。
そう考えると、どこかのタイミングで「見切りをつける」ことも必要です。
とりわけ、試験や課題の提出など「期限のある勉強」であれば尚更、この「見切り」が非常に重要。
どれか一つのことに時間を割きすぎてしまえば、他のことに割ける時間は短くなり、勉強の質も高めにくくなります。
とくに問題なのは、「見切り」をつけられずにダラダラと得意な教科の勉強を続けた結果、苦手教科に割く時間がなくなって勉強のクオリティが下がってしまうこと。
僕も何度か経験がありますが、苦手教科の勉強のクオリティが下がると得点への影響も大きいし、後で取り返すのも本当に大変です。
そういう意味でも、苦手教科は本来、他の教科に比べても多くの時間をかけてじっくり対策を積んでいくべきなのに、それができなくなってしまうのは避けるべきだと僕は思います。
②初めから苦手教科にコツコツ取り組む!
というわけで僕は、勉強の優先順位に迷ったら、「まずは苦手教科に手をつける」ことに決めていました。
「苦手教科の勉強のメドがある程度たってから、得意教科の勉強も進めていく」作戦です。
僕の場合、数学は最も苦手としていた教科の一つ。
どうせ途中で行き詰まるのはわかりきっていたので、あえて最初に取り組み始め、「あとどれくらい勉強すれば"それなりに"理解できるか」というメドを感覚的に掴むようにしていました。
苦手教科の場合、問題集などに何度か取り組まなければ理解できなかったり、1つの問題を考えるのに時間がかかったりすることも少なくありません。
それを見越して、あらかじめ多めに時間を作っておくのが、僕の作戦でした。
もちろん、そのままずっと苦手教科だけ取り組んでいては元も子もないので、途中で他の教科の勉強も組み込んでいきます。
苦手教科に粘り強くコツコツと取り組みつつ、いわば"息抜き"として得意教科も進めることができれば、精神的にもポジティブに勉強することができると思います。
ここまで書いてきたように、「苦手教科をメインに取り組むことを前提にしつつ、合間に得意教科も進める」という型を作ってしまえば、苦手教科から逃げることなく取り組むことができます。
「つい、得意教科ばかりに取り組んで、苦手教科の対策が疎かになってしまった」ということを防ぐためにも、オススメの方法です!
場面2:予習?復習?
さて、少し視点を変えて、「予習と復習の、どちらを優先すべきか」について書いていきます。
僕の結論は、「教科ごとに、使い分けるのがベスト!」です。
大前提として、予習であろうと復習であろうと、学校の課題として出されていたり先生に指示されたりした場合には、それをきっちりクリアしていくべきです。
僕自身、学校の課題や先生の指示は、少し自分の勉強スタイルとは違ったとしても、きちんと終わらせるようにしていました。
そのうえで、僕は、「予習がメインになる教科」と「復習がメインになる教科」があると思っています。
例えば古典は、僕の考えでは「予習がメインになる教科」の代表例。
きちんと予習をして、単語の意味や品詞の活用などを理解して(あるいは、「わからないところを特定して」)から授業に臨まないと、そもそも先生の解説がわからないことも少なくなかったからです。
反対に数学は、「復習メインの教科」だと思っています。
授業で学んだことを、何度も問題を解きながら定着させていくことが大切になります。
もちろん、両者とも、授業前に予習が十分にできるならやった方がよいに決まっていますし、試験前になれば教科に関係なく復習をすることになるでしょう。
ただ、毎日のように授業は行われるわけで、その都度「予習も復習も完璧にする」のは(理想はともかく)現実的には大変なことも多いと思います。
そう考えると、上記のように「とくに予習が欠かせない教科」や「復習を通じて知識を定着させていく教科」など、ある程度の区別は必要になります。
先ほど挙げた古典や数学の例は、あくまでも僕なりの捉え方です。
「この教科は授業の進行が速いから予習しておこう」とか、「予習はするけど、教科書をサッと見るだけで済ませて、復習を重視しよう」などと、教科ごとに、個々人に合ったスタイルを作っていくことをオススメします!
場面3:テスト勉強?受験(模試)の勉強?
ここでは、「テスト勉強と受験勉強はどちらを優先するか」についても触れます。
僕自身は、原則的にはテスト勉強を優先する方針で、勉強の計画を作っていました。
よく、「学校のテストがあるけれど、模試の勉強(受験勉強)もしたくて迷ってしまう...」といった高校生の声をききます。
僕自身、受験生になる前から、「学校のテストもあるけど、模試の勉強をしたいな」と思った経験が何度かあります。
ただ、模試の場合は間違えても成績に反映されることはなく、後で復習すればかなり使い倒せるのに対して、テストは「得点がそのまま成績に反映される」もの。
僕自身は推薦入試を視野に入れていたこともあり、成績を軽視することはできませんでした。
そこで僕は、原則としてテスト勉強をきちんと行い、余裕があれば模試のための勉強もするようにしていました。
テスト対策をきちんと進めることで授業の要点を復習する習慣がつき、模試の際に知識を思い出せることも増えました。
そうした経験もあり、僕は「テスト勉強を充実させれば、ある程度は受験/模試の勉強にも繋がる」と考えています。
それに、テスト勉強と模試などの勉強は「どちらかを選ばなければいけない」ものではありません。
テスト勉強は模試や入試本番の対策としても十分に使えます。
テストの出題と模試などの出題が被るかどうかはともかく、学校のテストも「入試に向けて絶対に抑えておいてほしいこと」を先生が厳選して作られていることが多いと思います。
言い換えれば、テストの内容を完璧にしておくことで、入試本番まで使える知識は身に付けられるということ。
「テスト勉強なんて、入試には役立たない」などと思わず、毎回のテスト勉強にも時間を作ることを強くオススメします!
まとめ:「自分なりの優先順位」をつけて効率的に!
ここまで、大きく分けて3つの場面に分けて、「優先順位の考え方」を書いてきました。
「得意か苦手か」「予習か復習か」「テスト勉強か模試(受験)の勉強か」、いずれを優先すべきかは、多くの高校生が経験する悩みだと思います。
ここまで書いてきたことがそのまま参考になればもちろんうれしいのですが、本当に大切なのは「自分なりの優先順位を考えて、実践する」ことだと、僕は考えています。
というのも、その時々の成績や勉強の進み具合によって、優先すべき取り組みが変わるのは当然だから。
ここに書いた内容は、あくまでも考え方のヒントとして、「自分だったら○○の勉強を優先する」などと方針を決めていきましょう。
自然と、自分が最初にやること・次に取り組むことなど、勉強全体の方針が作れるようになると思いますよ!
その勉強法の悩み、自分と似た先輩のアドバイスで解消しよう!
高2が始まってはや2か月。
授業スピードは一気に上がり、内容も難しくなったと感じているなら勉強法を見直すチャンスです!
そして、自分のトクイ・ニガテ、学習スタイルによりあった勉強法が知れるとうれしいですよね。
そこで役立ててほしいのが「文理別学習法データベース」。
全国の約150大学の先輩たちの合格につながる体験談がたくさん詰まった場所です。
データベースを使うときは、「自分に似たコーチを探す」機能がおすすめ。
文理、得意科目、苦手科目、さらには部活、学習スタイルから、自分に合う先輩に絞ってアドバイスを見ることができますよ!
<この記事を書いた人>
名古屋大 サンライズ
実は現在、留学しています。課題を進めるのも大変ですが、ここでも「勉強の優先順位」は大切...!受験生の頃を少し思い出しながら、今日も英語の論文を読んでいます。
※この記事は、公開日時点の情報に基づいて制作しております。


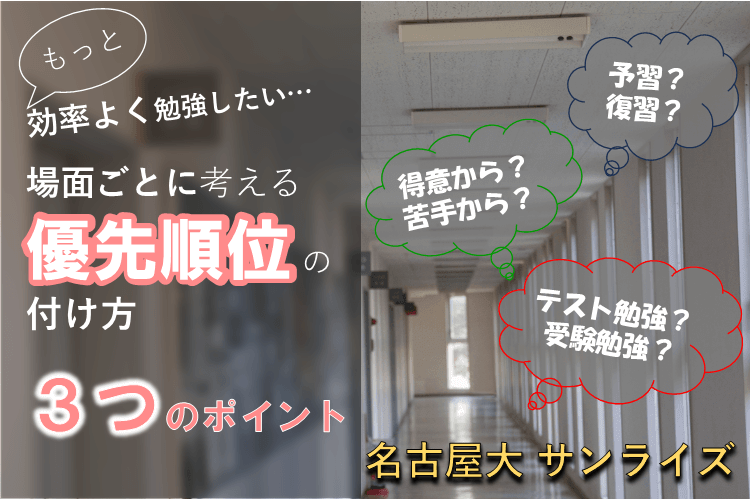





記事にコメントする
【コメント送信前に必ずお読みください】
このコメント欄では、質問や相談はできません。