
こんにちは!
立命館大学情報理工学部の霜月です。
受験生のみなさんは最後の1年が始まり、今までより一層気を引き締めているところだと思います。
そこで今回は、みなさんが大学生活にイメージがわきやすくなるよう、高校の授業に比べて大学の授業のスゴイところを紹介したいと思います!
ぜひ最後まで読んでいってくださいね!
専門性の高さと自由な学問選択
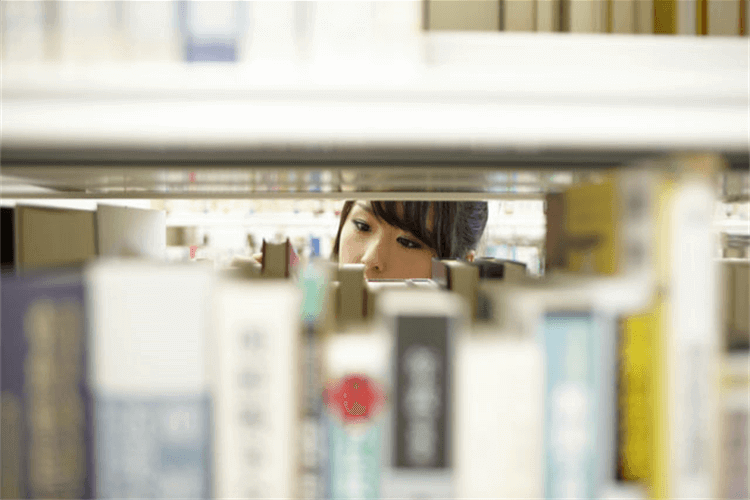
大学の授業の最大の特徴は、その「専門性の高さ」にあります。
高校では文系・理系の選択はあるものの、カリキュラムがある程度決まっており、教科書に沿った基礎的な知識を幅広く学ぶのが中心です。
しかし大学では、自分の興味に応じて学部・学科を選び、さらにその中で専門的な知識を深掘りして学ぶことができます。
例えば、生物学に興味があれば「分子生物学」や「遺伝学」などの授業を選び、文献を読みながら大学院レベルの知識にも触れることができます。
講義によっては、実際の研究データや最新の論文を扱うこともあり、知的好奇心を刺激されます。
また、他学部の授業を履修できる「履修自由度の高さ」も魅力の一つで、自分の専門にとどまらず、多角的な視点で学問を広げることが可能です。
これにより、自分だけの学びの道を設計できるのが大学ならではのスゴイ点です。
教授陣の知識と研究の第一線での授業

大学では授業を担当するのが、学問分野の第一線で活躍する「教授」や「准教授」といった研究者たちです。
彼らは日々、自らの研究テーマに取り組みながら、学生にその成果や最新の理論を伝えています。
そのため、授業内容も単なる知識の暗記にとどまらず、「なぜこの理論が重要なのか」「現在の研究ではどんな発展があるのか」といった、最先端の話題に触れることができます。
高校では、教員が教科書をベースにわかりやすく授業を進めるのに対し、大学では教科書が存在しないことも多く、教授のオリジナルな資料や論文を使って授業が行われる場合もあります。
中には、教授自身が執筆した教科書を使って講義を行うこともあります。
こうした環境の中で学ぶことで、知識をただ受け取るのではなく、自分で問いを立て、考える力が養われていきます。
知的刺激の多さという点でも、大学の授業は圧倒的にスゴイです。
学びのスタイルの多様さと自己責任

高校の授業は決められた時間割に従って行われ、出席も義務であり、先生が丁寧に進度を調整してくれます。
一方、大学では「学びのスタイル」が大きく異なります。
自分で時間割を組み、出席や課題、試験の情報を自ら管理する必要があります。
授業によっては出席を取らない場合もあり、「学ぶかどうか」は完全に学生の自由です。
しかし、その自由の裏には「自己責任」という重みもあります。
課題を怠れば単位を落とすし、試験範囲も大体しか教えてくれないこともあります。
反面、それを逆手に取れば、自分の生活スタイルや学びたいペースに合わせて授業を選ぶことができ、効率的かつ主体的に学習を進めることができます。
また、オンライン授業、ゼミ形式の少人数授業、実習やフィールドワークなど、授業形態も非常に多様で、学び方の選択肢が広いのも大学の特徴です。
自分に合った学び方を見つけられれば、学問がもっと楽しく、奥深いものになります。
まとめ
大学の授業は高校と比べて、専門性の高さ、教授陣による最先端の内容、そして自由度の高い学びのスタイルという点で大きく異なります。
自らの興味や関心に合わせて主体的に学べる環境が整っており、知識を深めるだけでなく、自分で考える力や学ぶ姿勢も育てることができるのが大学ならではの魅力です。
大学の授業を楽しみに、ぜひ受験勉強がんばってくださいね!
今回はミライ科の記事ということでまとめましたが、書ききれていないことがたくさんありますので、気になった方はぜひ先輩ダイレクトから先輩に聞いてみてください!
自分が志望する大学の先輩を指名して質問すれば、より近い回答が得られること間違いなし!
それではまた!
<この記事を書いた人>
立命館大 霜月
※この記事は、公開日時点の情報に基づいて制作しております。







記事にコメントする
【コメント送信前に必ずお読みください】
このコメント欄では、質問や相談はできません。