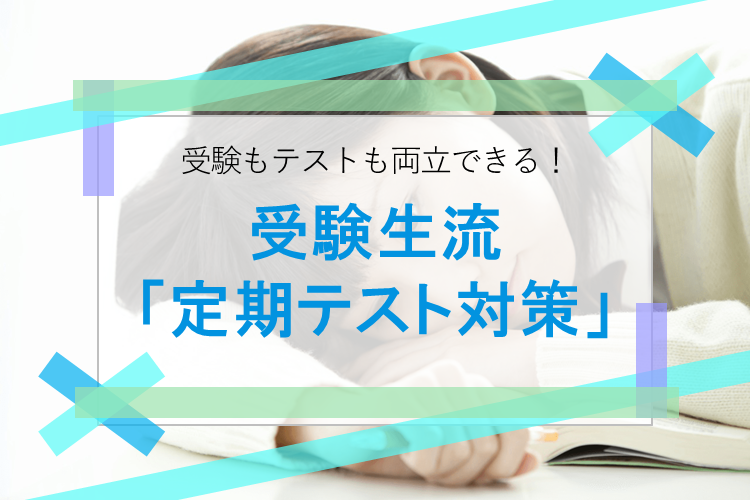
名古屋大学のオーガスです。
今回もよろしくお願いします!
ゴールデンウィークが終了しましたが、勉強モードにに切り替えることができていますか?
朝晩は寒く感じて日中は汗ばむほど暑い日もあり、体調を崩しやすい季節になりましたが、体調管理をしながら勉強を頑張るのはなかなか難しいかもしれません。
しかし、受験生になりましたから、受験に対する意識を高めていかなければならない時期ですよね。
そのような中、定期テストの時期もだんだんと迫ってきいて、受験勉強と定期テスト勉強をどのように両立していけばよいのか迷っている人が多いのではないでしょうか。
今回はそんな皆さんに、私自身の経験を踏まえて受験勉強と定期テスト勉強を両立するための受験生流定期テスト対策法を紹介したいと思います。
私が紹介する2つのポイントを参考にして、受験生流「定期テスト対策」をしていこう!
ポイント1:まずは合格への100題をやってみる!
「まだまだ入試レベルの問題を解くことができるレベルまで仕上がっていないのに、いきなり合格への100題を解くの?」と疑問に思う人が多いと思います。
たしかに、まだ履修し終えたばかりの単元がある人もいると思いますし、もっと勉強をして完璧にしてから入試レベルの問題を解き始めたいと感じている人もいるかもしれません。
しかし、受験対策と定期テスト対策を両立するうえで、どのように勉強をするべきなのかの戦略を立てるためには、まずは、入試レベルの問題はどれぐらいの難易度なのかを理解しておく必要があると思います。
実際、私が受験生のこれぐらいの時期に、合格への100題に挑戦してみましたが、問題を解くのに時間がかかりすぎていること、想像以上に難易度が高いこと実感しました。
これを知ったおかげで、定期テスト勉強をする際にも、速く解く訓練を兼ねて、タイマーで時間を意識して解く練習できました。
定期テスト範囲になっている単元だけで構いませんから、合格への100題の問題にチャレンジしてみましょう。
ポイント2:受験と定期テストの関連性が高い教科や分野を優先する!
二つ目のポイントは、受験と定期テストの関連性が高い教科や分野を優先して勉強をするということです。
具体的に言うと、定期テスト勉強が受験勉強に直結しているのかどうかを考えてみると良いということです。
例えば、私が高校生の時には、現代文の定期テストでは、授業で学習した文章を題材とした問題が出題されていました。
その文章が入試本番で出題される確率は極めて0に近いですから、受験のことを考えると勉強の優先順位は低くなります。
また、入試では利用しないつもりであるのにもかかわらず、定期テストの科目になっているものに関しても優先順位は低くなります。
一方で、古文で出てくる古文単語を暗記することや長文読解に出てくる英単語を覚えることは、受験対策に直結しているので、優先順位は高くなると思います。
数学や理科などの理系科目は、定期テスト対策の勉強が比較的受験に直結しやすいので、迷ったら理系科目を勉強してみるのもよいですね。
以上の2つのポイントを参考にして、定期テストと受験の対策を両立してきましょう!
①まずは合格への100題をやってみる!
②受験と定期テストの関連性が高い教科や分野を優先する!
ぜひ試してみてください。
何か悩みがあれば、ぜひ先輩ダイレクトで質問してね!!
<この記事を書いた人>
名古屋大工学部 オーガス
※この記事は、公開日時点の情報に基づいて制作しております。
※他の大学の先輩記事や入試情報はコチラで読み放題!


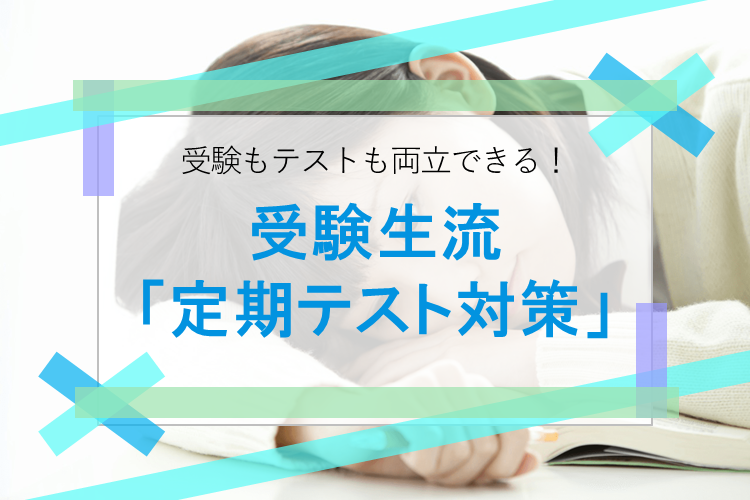





記事にコメントする
【コメント送信前に必ずお読みください】
このコメント欄では、質問や相談はできません。