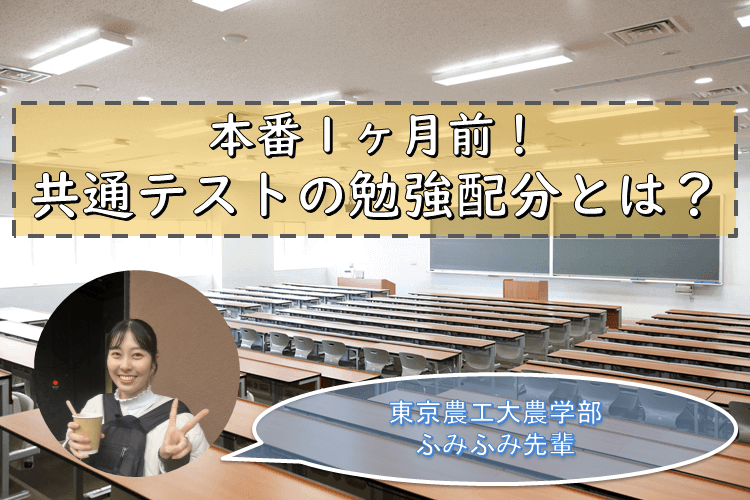
こんにちは!東京農工大農学部のふみふみです!
最近になって、一段と寒くなってきましたね...!
皆さんは体調を崩したりしていないでしょうか?
私は先日働きすぎて風邪をひいてしまい、色々とスケジュールがずれてしまったので、無理は禁物だということを思い知らされました(笑)
さて、そうこうしているうちに共通テストまで1ヶ月といったところでしょうか。
そろそろ本番を見据えて、共通テスト中心の勉強を始めている人が増えてくる頃かと思います。
そこで今回は、【共通テスト対策の勉強配分】についてお話していきます!
それでは、早速本題に入ります!
①志望校の得点配分で決める!
私の場合だと、志望校の得点配分が[共通テスト:二次試験=900:700]であったため、共通テストの点数が高い人の方が若干有利になる得点配分でした。
個人的に、共通テストの得点配分の方が高い大学を受験しようとしている人は、8~9割を共通テスト対策に充てていいと思います!
理由としては、やはり共通テストで得点できていた方が、二次試験までの安心感につながるし、単純に総合得点が高くなりやすいからです。
国公立受験だと、どうしても二次試験対策を頑張らなくては!と思う人も多いと思うのですが、どういう得点配分であれば合格点に到達できるのかを逆算して、勉強の配分をすると良いのかな、と思います◎
また、この時期にほぼ二次試験の勉強をしない!というのも一つの手なので(私はこのタイプでした!)、自分の勉強スタイルに合わせていきましょう!
②具体的に何をしていたのか?
私が受験生だった時のこの時期は、共通テストやセンター試験の過去問や共通テスト対策の問題集、実践問題などを解いて復習する、というのをひたすら続けていました!
また、復習をして知識が抜けていたり、もう少し簡単なところに戻った方がいいと思ったりしたところは、普段自分が使っている問題集を使って、穴埋めをしていくことを意識していました。
個人的に当時感じたのは、実践問題などを解いて慣れることも大切だけど、結局インプットしないと点数は上がらない、ということです。
原理は定期テストと同じで、ある程度知識の詰め込みも通用します!
ですので、共通テスト対策は実践演習だけではなく、基礎や知識の部分にしっかり取り組む日があると、より伸びるのではないかと今になって思います。
色々と話してしまいましたが、【演習と復習の両方が大事】ということです!
まとめ
今回は、【共通テスト対策の勉強配分】についてお話してきました!
残り1ヶ月、悔いの無いように共通テスト対策をしていってほしいです。
ただ、元気でいることが一番大切なので、無理せず健康第一で年末をお過ごしくださいね^^
応援しています!!
また、何かわからないことや不安なことがあれば、いつでも先輩ダイレクトで質問を受け付けています♪
<この記事を書いた人>
東京農工大農学部 ふみふみ
※この記事は、公開日時点の情報に基づいて制作しております。


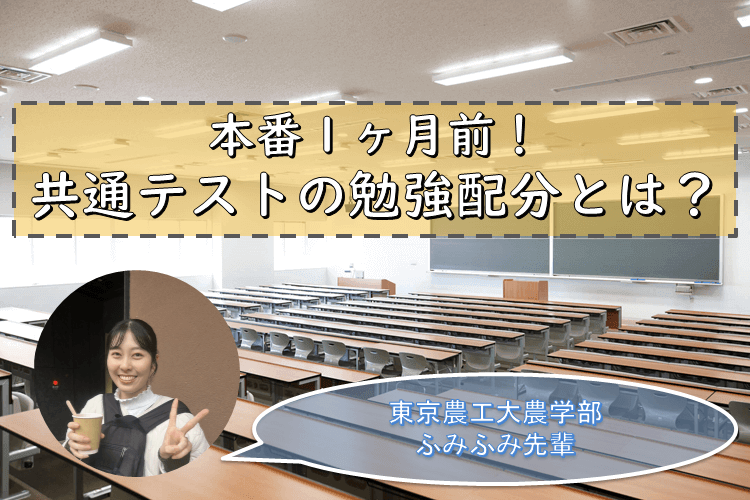





記事にコメントする
【コメント送信前に必ずお読みください】
このコメント欄では、質問や相談はできません。