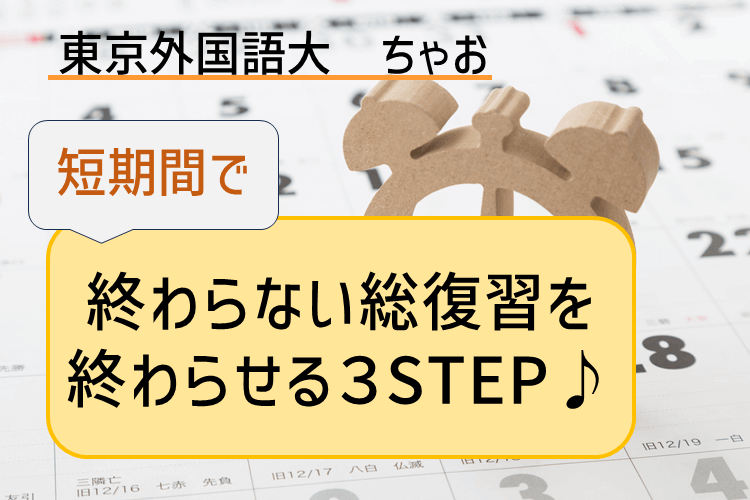
こんにちは!
東京外国語大学国際社会学部のちゃおです。
外大はつい先週学祭を終えまして、通常の生活に戻っていっている中です。
大学のお祭りは高校までとは規模が異なり、たくさんの人でにぎわうので、とても忙しくも楽しい時間を過ごせました!
11月ももう終わり、いよいよ共通テスト当日が見えてきましたね。
しかし、今この時期にまで部活や文化祭等で思うように勉強時間が取れず、全範囲を復習しきれていない方もいるのではないでしょうか...?
今回は、そんな方々に朗報!
短期間で総復習できる勉強方法を3つ伝授します!!
勉強しなければいけない量がとんでもなく、途方に暮れている人も、何から手をつけて良いか迷っている人も、この方法を使えば迷わずにどんどん勉強を進められるはずです!
【STEP1】過去問を解いてみよう!
復習が終わるまでは過去問は解けない...
そう思っていませんか??
実は、効率の良い総復習方法とは過去問をやってしまうことなのです!
なぜ総復習をしているのでしょうか?
出題範囲が全体に及んでいるからですね。
つまり、逆に考えると、問題を解いていけば自然と全出題範囲に触れられるということです!
いきなり過去問なんて難しい...と渋っているかもしれませんが、最初は高得点を取ることを目標にせずに、
・どの範囲が出やすいのか
・どのような出題形式で出るのか
・自分の特に苦手な範囲はどこか
ということを見つけ出すために、と意識してやってみましょう!
【STEP2】苦手な範囲を解き直そう!
過去問を解いてみたあとは、自分の「ニガテ」を把握しましょう。
解いてみて思うようにペンが進まなかったところ、採点してみて特に点数が低かった「大問」を見つけます。
ここでなぜ「大問」なのかというと、どの教科も大体大問ごとに出る範囲が固まっているからです!
例)国語の大問1は評論読解、数学1Aの大問5は図形の問題
理科社会は、毎年数字の変動はありますが、大問ごとに大体1分野が出題されます。
次に、過去問で見つけた自分の苦手な「大問」や分野を、今までの模試や残りの過去問を使って先に解いてしまいましょう!
ここでのポイントは、特定の大問だけたくさん解くことです!
ニガテを克服するためにも、出題される形に慣れるためにも、というどちらの目的も達成できる勉強方法でございます。
【STEP3】間違えをストックしていこう!
ただひたすら問題を解くだけでは、復習しても身についたことにはなりません。
どこが苦手なのか見返すためにも、間違えたことをストックしていく必要があります!
採点して間違えた問題や解き方に不安があった問題があれば、どこでつまづいたのかはっきりさせましょう。
そして、理解しきれていなかったこと・新たに覚えたことを教科書やノートなどに書き留めておきます。
この書き留めたメモ書きは、試験直前に見直す目印になっていました。
同じところを間違えていたら、メモ書きを強調させたり、付箋を貼ったりなどしていました...!
同じ間違えはもうしないぞ、という戒めにもなります。
まとめ
今回は、短期間で総復習を終わらせる方法をお伝えしました!
1 過去問を解く
2 苦手な大問を解く
3 間違えをストックする
以上の3点を意識して、ぜひ復習と演習を同時に進めていってください!
共通テスト当日まで、一緒に走り抜けましょう!
応援しています!!
<この記事を書いた人>
東京外国語大 ちゃお
※この記事は、公開日時点の情報に基づいて制作しております。
※他の大学の先輩記事や入試情報はコチラで読み放題!


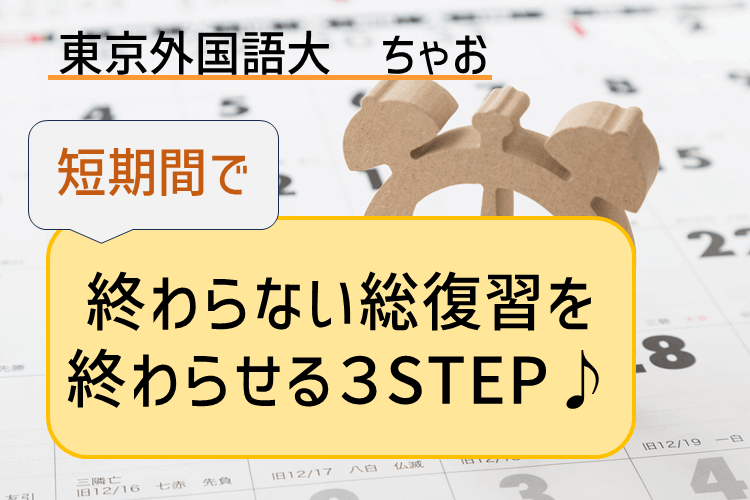





記事にコメントする
【コメント送信前に必ずお読みください】
このコメント欄では、質問や相談はできません。