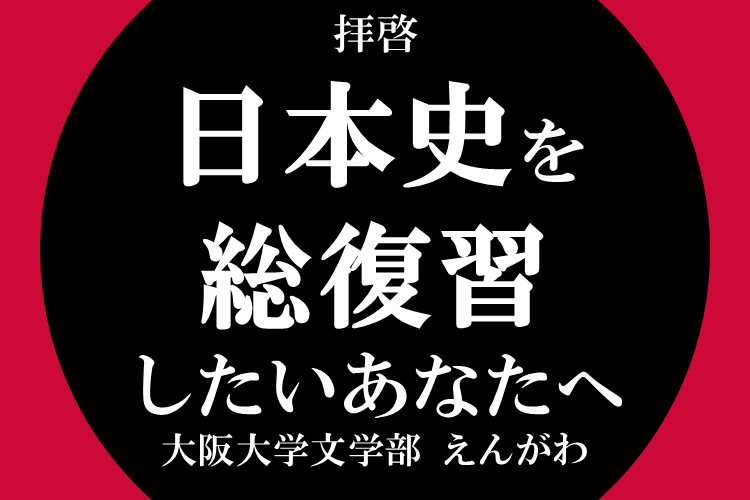
こんにちは! 大阪大のえんがわです。
「まだ暑い」なんて言っていたら、いつの間にか冬になっていました。
「まだ時間がある」と思っていたら、いつの間にか本番まで100日を切っていたあの頃の記憶がよみがえります。
さて、皆さんにはやろうと思っていながら終わらなかった「全範囲総復習」、ありませんか?
私には、ありました。
日本史B選択で、共テでも二次試験でも日本史を使う私は「夏休みに日本史を総復習するぞ!」と意気込んだはいいものの、途中で力尽き。
本腰を入れたのはちょうど今頃、本格的に寒くなってきてからでした。
今回は、日本史を総復習をするにあたっての5つのアドバイスを私の実体験や失敗をもとにお伝えしたいと思います。
用意するもの
本題に入る前に、私が総復習に使った教材は以下の通りです。
・教科書準拠の書き込める問題集(単語が書けるか確認)
・教科書(書き込んで流れの確認)
・授業プリント(授業中のメモなどを見返す)
・合格への100題(二次試験対策+α)
・一問一答(通学時間で見る)
特別なアイテムは使っておりません、ということを主張しておきます。
なんだかんだ教科書が最良の教材だと思っています。
では、本題の5つのアドバイスを始めましょう。
①まとめノートはピンポイント
とりあえずで、まとめノートを作ろうとしていませんか?
はっきり言って、時間がありません。
効率的に進めるならまとめノートはピンポイントにしましょう。
例えば私は「蝦夷の征討史」や「神道史」といった超限定的なまとめをルーズリーフに書き込んでミニまとめノートとしていました。
このとき、合格への100題や大学受験チャレンジに載っている様々な年表に助けられました。
他にも、市販の日本地図の付せんがかなり役に立ったのでオススメしておきます。
②文化は時代背景とセット
文化は覚えることが多い!
つい単語を覚えるのに終始してしまいがちですが、私が重要視したのはその文化が生まれた時代背景です。
こういう時代背景があったからこの文化が生まれ、こういう世相だったから次の文化が生まれる......という風に。
論述問題しか出ない大阪大学の二次試験対策として、とにかく歴史の流れを大切にしていました。
③好きな時代ばっかり勉強するな
やりがちです。
私の場合は好きな古代ばっかり勉強してニガテなことが分かっていた近代を敬遠していたため、直前に焦りながら一から勉強し直す羽目になりました。
あなたがニガテな時代こそ出ると思いましょう。
④一問一答にとらわれるな
一問一答は非常に便利です。
覚えていない単語が洗い出せます。
逆に言えば、それだけです。
単語同士のつながり、時代の変遷の過程などは教科書などで俯瞰する必要があります。
共テの日本史は一問一答形式ではありませんよね。
大阪大の二次試験の日本史はすべて論述問題なのでよりいっそう。
何度でも言いますが、総復習するうえで大切なのは、歴史の流れを押さえることです。
⑤模試を活用せよ
「総復習が間に合う気がしない!」と思っているあなた。
絞りましょう。
具体的には、ニガテだと自分で分かっている時代や文化、模試で出来なかった範囲に絞って復習します。
私は模試で洗い出された覚えていない単語、範囲を付せんに全部書き出していました。
そこであまりの近代のニガテさが露呈し、やっと近代に向き合う覚悟ができました。
模試は自分と向き合える機会ですね。
まとめ
以上、日本史を総復習したいあなたへの5つのアドバイスbyえんがわでした。
歴史科目を勉強するなら「歴史の流れを完ぺきにすること」これに尽きます。
どうしても単語の暗記に必死になってしまいがちなので、必ず歴史を俯瞰することを忘れずに。
この記事があなたの助けになれば幸いです。
本番が近づくにつれ、寒さは厳しくなると思います。
どうか身体を温かくして、あなたのこころと体調に気を遣ってくださいね。
<この記事を書いた人>
大阪大 えんがわ
冬は嫌いだけど、飼い猫が一緒に寝てくれる季節なので複雑なきもち。
※この記事は、公開日時点の情報に基づいて制作しております。
※他の大学の先輩記事や入試情報はコチラで読み放題!


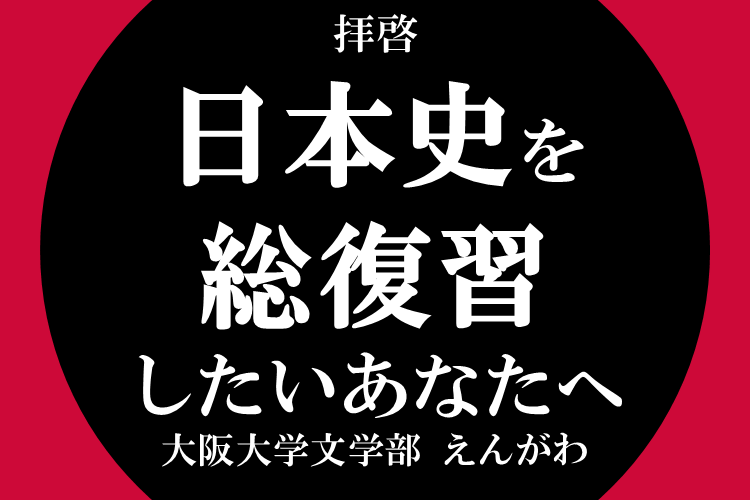





記事にコメントする
【コメント送信前に必ずお読みください】
このコメント欄では、質問や相談はできません。