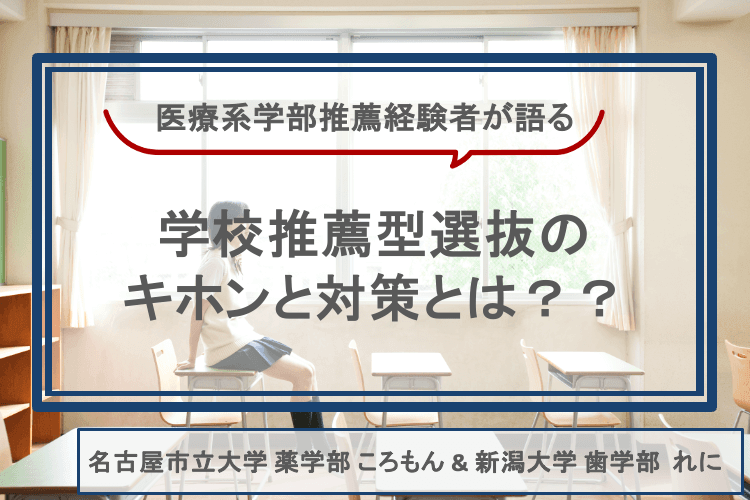
こんにちは!
名古屋市立大学薬学部のころもんと新潟大学歯学部のれにです。
今日は学校推薦型選抜を経験した2人で記事をお届けしたいと思います!
私達は、2人とも学校推薦型選抜の受験を決めたのは高3の夏休みごろと少し遅めでした、、、。
短期間で集中して対策するために意識したことをお伝えできたらと思います!
今回は、①志願理由書、②面接、③一般入試との両立 の3点についてお話します!
推薦入試といっても大学や学部によって、入試形態や対策方法も様々だと思うので、ぜひ今のうちから推薦入試を一つの選択肢として考えるきっかけになる記事になればうれしいです!
①志願理由書はいつから書いた?どんな内容?
ころもん:
私は、学校推薦型選抜の受験を決めた夏休み明けから書き始めました。
字数制限が500字以内だったので、薬学部に興味を持ったきっかけ、大学でどんな研究をしたいか、将来はどんな薬剤師になりたいか、そのために在学中にどんな力を身につけたいか、という観点から書きました。
志望大のアドミッションポリシーを読んで、どんな受験生を求めているのか意識して文章を組み立てていきました。何度も書くことによって、自己理解にもつながり面接対策の役に立ったと感じています。
れに:
私は、夏休み中に志願理由書を書くために必要な情報の収集を始めました。
志願理由書を実際に書き始めたのは、ころもんさんと同じく夏休みに入ってからです。
内容は、歯学部を目指したきっかけ、どうして志望大の歯学部でないといけないのか、将来像、歯科医師となる上で自分のどのような点を活かすことができるのか、について書きました。
高校の先生に何度か添削してもらうことで、不足している部分・不必要な部分、文章の言い回しなどを何度か書き直して、要点がしっかりと伝わるような志願理由書になるようにしました。
②面接対策はどんなことをしていた?
ころもん:
私は、面接の中に化学の口頭試問が課されていたので、先生との面接練習の他に、化学の教科書をよく読むようにしていました。
化学現象を自分の言葉でわかりやすく説明することが難しく、何度も化学の先生にご指導をいただきながら練習を重ねました。
また、面接では時事問題にも対応できるように、日頃から志望分野についてニュースをよくチェックするようにして、情報を集めていました。
先生との面接練習を通して、「どうしてこの大学の学部学科じゃなければダメなのか?」という点を掘り下げられるように、自分なりのこだわりを持つようにしていました。
れに:
私は、高校で配布された「予想質問集」のプリントを参考に、夏休み終盤あたりから面接ノートを作成して、一つひとつの質問に対してどのような回答をするかをまとめることを始めました。
ノートを作成する上で気をつけたことは「文章でまとめない」ということです。文章でノートにまとめてそれを暗記してしまうと、本番で思い出せなくなった際に対応するのが難しくなってしまうからです。
あくまでノートには要点のみをまとめることで、ポイントポイントで覚えて、言い回しなどは面接練習を重ねることで応用を効かせられるように意識していました!
面接練習で新たに聞かれた問題があった場合には、さらにノートに追加することで、一度聞かれたことのある質問に対しては、本番でもスムーズに答えられるように対策をしました。
面接対策には何より練習を重ねることで、空気感にも慣れることができたので、可能な限り先生と練習をしてアドバイスをいただくようにしていました。
③一般入試対策との両立にどうやって取り組んだ?
ころもん:
学校では、志望理由書に書く内容を考えたり先生との面接練習をしていました。家に帰ってからは、共通テスト対策や二次試験対策の時間にして、メリハリをつけていました。
また、私の志望大の小論文では化学の問題と英語の要約問題も課されていたため、共通テストや二次試験を見据えながら勉強を進められたと思います。
時間を決めて取り組むことで、いい意味で焦りが生まれ、集中して日々の受験勉強を進めることができたと感じています。
れに:
私の志望大では、面接・小論文に加えて共通テストの成績も試験内容の一つだったので、特に共通テスト対策に力を入れていました。
普段は共通テスト対策、二次試験対策中心に行っていました。勉強の合間など、やる気の継続が難しい時などに、小論文の対策を間に挟んでみたり、面接ノートを見返したりしていました。
特に小論文に対しては、英文出題だったので、英語に関して一般入試対策も同時に行う気持ちで取り組むようにしていました。
一般入試対策を続けているとどうしても煮詰まってしまうことが多かったので、私の場合は推薦入試対策をすることで、一度リセットして勉強を再開することができました!
まとめ
今回は医療系学部の学校推薦型選抜の経験談をお伝えしてきました!
志願理由書の他にも、小論文、口頭試問、共通テスト対策...とやらなければいけないことがたくさんありますが、大学によって様々です!
ぜひ、志望大学の学校推薦型選抜について調べてみてくださいね。
最後に2人からひと言ずつお伝えして締めくくろうと思います!
ころもん:
限られた時間の中で、推薦入試の対策を平行して行うことは大変ではありましたが、志望大学合格のチャンスを増やすとても貴重な機会になったと感じています。推薦入試のために勉強したことは必ず、共通テストや二次試験にも活きてきます。ぜひ、学校推薦型選抜に積極的にチャレンジして欲しいと思います!
れに:
私は3年生になる前から、日々の定期テストに力を入れていたことで、高3の夏からでも推薦入試を新たな選択肢として考えることができ、そのおかげで志望大学に合格することができました!今のうちから、定期テストや学校行事、課外活動に力を入れることで、受験生になってから活きる部分がたくさんあると思いますよ!
記事を読んで、推薦入試ついてさらに気になることがあれば、先輩ダイレクトも活用して、情報を集めていただけたらと思います!
最後まで読んでくださりありがとうございました!!
<この記事を書いた人>
名古屋市立大学 薬学部 ころもん & 新潟大学 歯学部 れに
※この記事は、公開日時点の情報に基づいて制作しております。


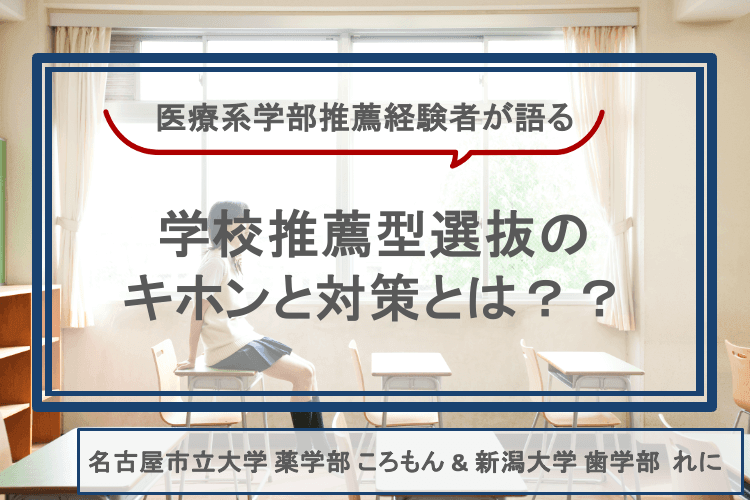





記事にコメントする
【コメント送信前に必ずお読みください】
このコメント欄では、質問や相談はできません。