こんにちは!立命館大学総合心理学部のこぴです。
寒さが増して、本格的に冬になってきましたね。寒がりな私は毎日凍えています笑
受験本番を控えた皆さんの中には、「そろそろ過去問をやらないと!でも、他にもやらないといけないことが山積みで余裕がない、、、」と、焦りを感じでいる方もいるのではないでしょうか。
今回は、国公立を受験した私が、共通テストと二次試験それぞれの過去問をいつどのように使っていたのかについて紹介していきたいと思います♪
①共通テストの過去問
私が本格的に共通テストの過去問に取り組み始めたのは、11月ごろです。
それまでは、共通テスト模試や学校の演習教材を復習するなどして共通テスト形式の問題に取り組んでいました。
国語、英語、数学については共通テスト形式の問題に慣れることが重要なので、時間をはかって本番さながらの演習をたくさんしていました。
特に国語と英語に関しては、期末テストが終わってから毎日交互にどちらかの教科の過去問を時間をはかって解いて、感覚を忘れないようにしていました。
同じ問題に何度も取り組むのではなく、過去問が尽きたら市販の予想問題集を使い、新しい問題でとにかくたくさん演習していました。
理科、社会系の科目は、一度説いた過去問に出てきた知識はすべて吸収することを目標に、間違えた問題は徹底的に復習して身に着けるようにしていました。
私の学校ではセンター試験時代の過去問も加え、約10年分の過去問が配られていたので、それらを解きながら知識を頭に入れていく作業を繰り返しました。
②二次試験の過去問
共通テスト前の11月、12月はほとんど二次試験の過去問に手を付けていませんでした。
10月ごろに問題傾向を知るために一年分だけ解いて、そのあとは合格への100題を中心に二次試験対策をしていました。
共通テスト前は、二次試験対策をしすぎると共通テストへの不安でかえって勉強に集中できなくなってしまったため、精神安定のためにも共通テスト対策を中心に勉強するようにしていました。
共通テストが終わってからは国語と英語は15年分の過去問集を買って、合格への100題よりも過去問を優先して勉強していました。
なぜなら、国語や英語は大学ごとに問題傾向がはっきりしており、志望校の問題形式を攻略することが重要になるからです!
一方数学は、合格への100題と過去問に同じぐらいの熱量で取り組んでいました。
過去問は5年分を何回も解き直していました。
数学は志望校の問題傾向に沿った対策をするというよりも、基礎知識を複雑な応用する力を養うことを目標にしていました!
以上が私の過去問の活用法です。
ただ、今やらなければならないことは人それぞれなので、「絶対にこの使い方が正解」と言い切れるものはありません。
また、「すべての教科の過去問を同じだけ完璧にやらなければいけない」というわけではありません。
たくさんの先輩の経験談を見て、参考にしたいと思ったものを自分のペースで少しずつ取り入れてみてくださいね。
応援しています♪
<この記事を書いた人>
立命館大 こぴ
※この記事は、公開日時点の情報に基づいて制作しております。
※他の大学の先輩記事や入試情報はコチラで読み放題!


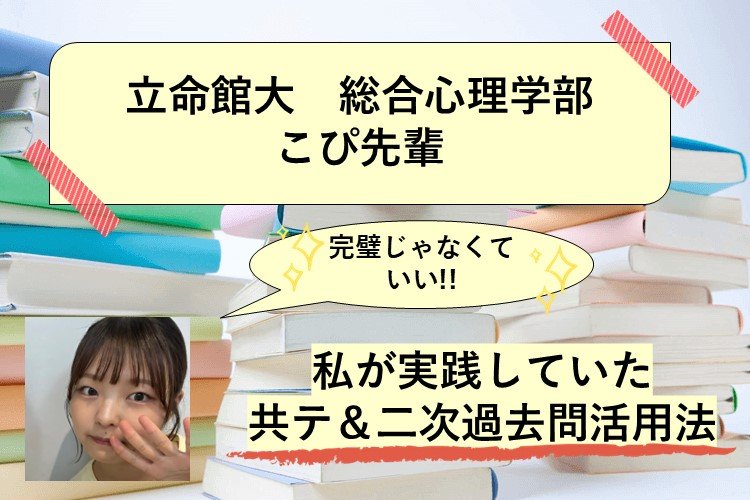





記事にコメントする
【コメント送信前に必ずお読みください】
このコメント欄では、質問や相談はできません。