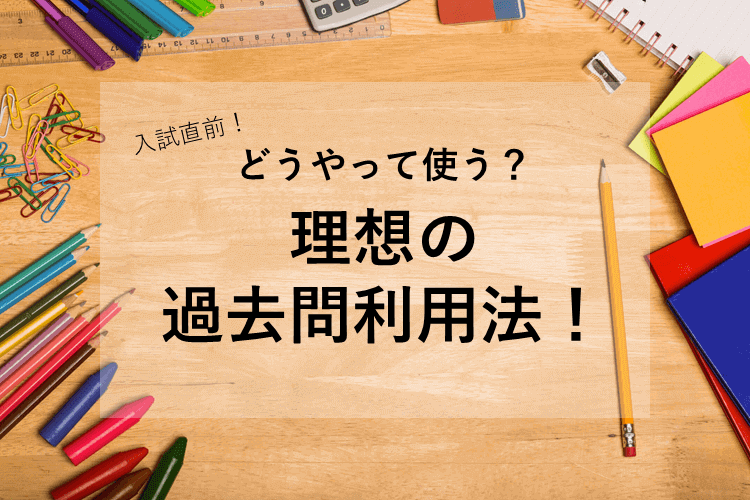
こんにちは!
名古屋大学工学部のりばです!
いよいよ共通テストまで残り約1ヶ月、2次試験も近づいてきましたね。
そんな中、過去問に取り組まなくてはいけないと思っている人が多いと思いますが、いつ・どのくらい・どのように使うべきか迷うこともあるのではないでしょうか?
過去問は志望校の傾向や出題形式を把握したり、自分の得意、苦手を把握したりするのにぴったりで、良問が多いのでたくさん解くことに損はありません!
そこで今回は、私の経験を元に、共通テストが近づいた今から本番までの2次試験の過去問の効果的な利用方法について時期別、受験校別に紹介したいと思います!
①共通テスト前(12~1月)
共通テスト前のこの時期は共通テストの勉強をすることをおすすめします!
まずは共通テストで高得点を取ることが志望校合格に一歩近づくために大事だと思います。
私も12月中は、主に共通テスト対策に集中していました!毎日毎日、学校でも家でも共通テストの演習ばかり解いていました。
ただ、私は理系なので、共通テストで数3が出題されない分、共通テスト対策に飽きてしまったとき、余裕があるときに志望校の数学の問題を数問解いていました。
もし、共通テストで出ない分野があって、忘れてしまうことが心配なときは、時々過去問などを解いて忘れないように努めましょう!
②共通テスト後(1月中旬~2月上旬)
共通テストが終わったら、2次試験の過去問を解きまくりましょう!
ただ解くだけではなく、本番と同じように時間を計って解いてみると、時間配分や問題を解くスピードもわかるのでおすすめです!
また、この時期は併願校の受験をする人も多くいると思います。
今まで志望校の勉強をしてきたからと言って、併願校の過去問を全く解かずに試験に臨むのはとても危険です。
そのため、問題形式に慣れるためにも2,3回は過去問を解いておくようにしましょう!
ちなみに私は、試験の2週間前ほどから過去問を解き始めました。
③2次試験直前(2月上旬~本番)
2次試験直前は、もしかすると近年の過去問を一通りといてしまって何をすればいいかわからなくなる人も出てくるかも知れません。
そんなときは、今までの過去問を解く中で、自分が苦手だと思う教科や単元に的を絞って、もっと昔の過去問まで探してたくさん練習しましょう。
大学によっては、教科ごとに過去20年分くらいの問題がまとめてある教材もあるので、それを使いながら集中的に取り組むことをおすすめします!
また、過去問は解いたら終わりではなく、解説を読んで自分の中で解き方を理解してこそ力がつくと思います。
いろいろな出版社が解答解説を出しているので、わからなかった問題はいろいろな解説を読んで、自分が一番納得できる解き方を見つけて自分の力にしましょう!
まとめ
時期ごとに、優先順位を決めて取り組んで過去問を上手に使い、志望校合格を勝ち取ろう!
①共通テスト前(12~1月)
②共通テスト後(1月中旬~2月上旬)
③2次試験直前(2月上旬~本番)
うまくいかないときや悩みがあるときは、ぜひ「先輩ダイレクト」で質問してね!
最後まで一緒に頑張ろう!
<この記事を書いた人>
名古屋大 りば
※この記事は、公開日時点の情報に基づいて制作しております。
※他の大学の先輩記事や入試情報はコチラで読み放題!


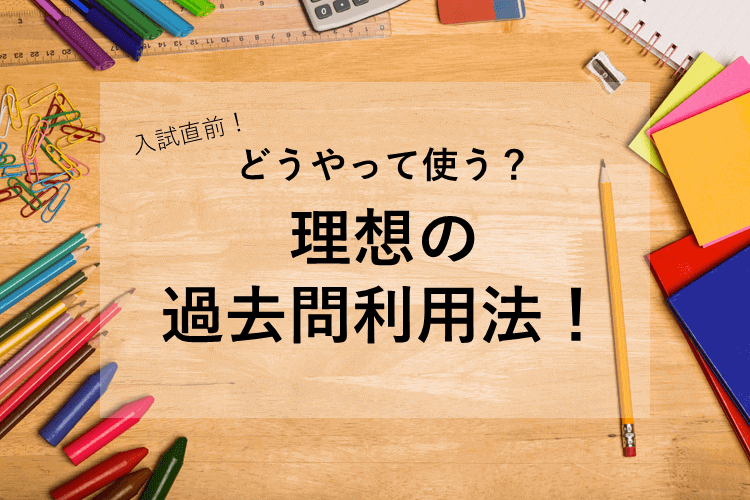





記事にコメントする
【コメント送信前に必ずお読みください】
このコメント欄では、質問や相談はできません。